断熱性能の高さは施工会社選びでキマる!? 失敗しない断熱材の選び方とコツ

断熱性能の高さは施工会社選びでキマる!? 失敗しない断熱材の選び方とコツのインデックス
家づくりの際に、どうしても家の間取りやデザインばかりに目が行きがちになり、家の性能まではじっくり検討できていないお宅は多いかもしれません。しかし、家族が快適に暮らしていくうえで、家の性能はデザイン以上に重要になることも。あとあと後悔しないためにも、家づくりの段階で断熱性能についてもしっかり考えてみましょう。そこで、失敗しない断熱材選びと施工会社選びのコツをご紹介します。
夏は暑く、冬は寒い日本の気候では、家の断熱材は欠かせない!
家族が快適に家に住み続けるためには、断熱材は欠かせない存在です。とくに、北海道や東北地方など冬の寒さが厳しい地域は、暖かい家づくりに断熱材はなくてはならないものですが、実は寒い地域だけには限りません。
断熱材は、夏の暑さをしっかり遮断して、冷房効率をあげる効果もあります。最近の夏は40度を超える日も多く、暖かい地域でもしっかりとした断熱性能が求められるのです。
つまり、暑い夏も寒い冬も快適に暮らすためには、日本各地のどの地域でも、断熱性能をしっかり備えた家を建てることが大切です。家の中を夏は涼しく、冬は暖かく室温をキープしてくれることで、各部屋の温度差が少なくなり、快適さもアップ。さらに、冷暖房などの光熱費を抑えることもできます。「断熱材選びは住宅の生命線」とまで言われるほど、現代の家では断熱材はなくてはならない存在なのです。
原料によって断熱効果も違う? 知っておきたい3種類の断熱材

断熱材とひと言で言っても、実はさまざまな種類があります。そして大きく分けると、原料の違いで「繊維系」「発泡プラスチック系」「天然素材系」の3つに分類されます。
<繊維系>
繊維系は「無機系」と「木質繊維系」に分かれます。繊維系は戸建住宅の断熱材の8割以上を占めていると言われています。
●グラスウール(無機系)……建築現場や家庭から回収されるリサイクルガラスを使用し、環境に優しい断熱材。日本では最もメジャーな断熱材でコストも安く、北欧や欧米でもよく使われています。原材料が不燃のため、耐火性能が高いのも特徴。ただし、職人の施工技術により、断熱性能に差が出やすいのがデメリットです。
●セルロースファイバー(木質繊維系)……原料に古紙を再利用した断熱材で、調湿性に優れていて、結露対策に最適です。さらに、防火性能や害虫予防にも効果的があり、オールマイティーな断熱材として使われています。専門業者による工事のため、施工精度の差が少ないのがメリットです。ただし、他の断熱材と比較するとコストが高くなります。
<発泡プラスチック系>
住宅用断熱材としてはまだ歴史が浅いのですが、高い断熱性能と施工の容易さから、注文住宅での採用が増加している断熱材です。
●押出発泡ポリスチレン……ポリスチレンを発泡させる製造方法で作られた断熱材。水や湿気に強いのが特徴で、軽いことで施工や運搬がしやすいというメリットがあります。シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでいないため、安全性にも優れています。デメリットは、コストが高いことと、熱に弱いことです。
●ウレタンフォーム……連続発泡された板状のものと、現場で吹付け発泡するタイプの2種類があります。小さくて硬い泡の集合体である「硬質ウレタンフォーム」の中には、熱を伝えにくい空気が閉じ込められているため、長期間に渡って優れた断熱性が期待できます。
<天然素材系>
天然素材は、安全で環境に配慮された断熱材。ホルモアルデヒドなど、健康を気遣う材料にこだわる人にオススメです。
●ウールブレス……原材料の70%が羊毛で作られている、自然素材の断熱材のひとつ。ウール繊維は縮れて複雑に絡み合い、中に空気をたくさん蓄えています。この空気層が外気を遮断するので、高い断熱性を得ることができます。さらに調湿性も高く、音を吸収したり、燃えにくいなどにメリットがたくさんあります。ただし、他の断熱材よりもコストが高いです。
●炭化コルク……コルク樫の樹皮から作られる断熱材。コルク樫は生命力がとても強く、樹皮を剥いでも数年で再生するエコな自然素材です。コルクはもともと断熱性が高い素材ですが、炭化させることで断熱性がさらにアップ。熱伝導率がとても低く、熱を伝えにくかったり、調湿性や防音性、防虫性に優れています。炭がホルモアルデヒドや気になる匂いを吸収してくれます。ただし、コストが高めです。
それぞれの材料の特徴を考え、家族のライフスタイルに合った断熱材を選びましょう。
断熱材選び以上に大切なのが、3種類ある施工方法
断熱材は、それを隙間なく敷き詰めて家を覆うことで、その性能を発揮します。つまり、大切なのは断熱材の種類よりも、それに合った工法でしっかり施工すること。そこで、3つの断熱工法をご紹介します。
■充填断熱工法
柱と柱の間などの空間に断熱材を入れて、吹込み充填する工法。木造住宅で広く用いられています。この工法のメリットは、ほとんどの種類の断熱材で使用でき、壁の内側空間を利用するため、外張り断熱工法に比べてローコストで施工ができること。また、断熱性能が劣化しにくく安定しています。デメリットは、柱と梁のつなぎ目などを避けながら気密・防湿シートを貼る必要があるため、施工方法が煩雑になる場合があります。
■外張り断熱工法
柱などの構造材の外側に断熱材を貼り付けていき、建物を覆う工法。メリットは躯体の外側に施工するので、内部のデザインなどに自由度が高く、施工後の確認も比較的簡単です。一方でデメリットは、充填断熱工法に比べてコストが割高で、経年劣化の不安があります。また、強い地震の際に変形する恐れがあります。
■付加断熱工法
充填断熱と外張り断熱の両方を施工する工法。充填断熱や外張り断熱だけよりも、断熱材を厚くできるため、断熱性能を高めやすい工法です。しかし、その分コストも増えるのがデメリットです。
施工会社を選ぶ際に、その会社ではどの断熱材を標準で用意しているか、またどの工法を採用しているのかを確認しましょう。
断熱の効果は、選ぶ施工会社次第ってホント!?

施工会社を選ぶときに、家のデザインの好みで選ぶことはもちろん大切です。しかし、デザインだけではなく、断熱性など高性能な家を建ててくれる会社であることも、同じように重要ですよね。それを見極めるのはなかなか大変なのですが、そのひとつの基準となるのが、ZEH(ゼッチ)に対応している会社かどうかです。
ZEHとは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」のことを指し、住宅の断熱性・省エネ性能を上げたり、太陽光発電などでエネルギーを創り出すことにより、年間のエネルギー量の収支をプラマイゼロにする住宅を指します。このZEHに施工会社が対応しているか、対応していないかは、断熱性や省エネ性能を重視している会社かどうかの、ひとつの基準になります。
ZEHの性能は以下の値などで表します。この数値が小さければ小さいほど、気密性・断熱性・遮断性に優れた高性能な家ということがわかります。
C値=気密性
数値が小さいほど隙間が小さくなり、気密性能に高くなります。気密性能が高くなると、断熱材の本来の性能が発揮され、室内が暖かくなります。
UA値=断熱性
数値が小さいほど熱が外に逃げにくくなり、断熱性能が高くなります。断熱性能が高くなると、暖房で暖められた室内の熱が逃げにくく、光熱費を抑えられます。
ηAC値=遮熱性
数値が小さいほど夏の日差しを遮り、遮熱性能が高くなります。遮熱性能が高くなると、日射による熱の侵入を抑えることができ、冷房が効きやすく光熱費も抑えることができます。
この数値をホームページなどで公表している施工会社もありますので、それをひとつの目安にしてみるのもいいかもしれません。
断熱材にはさまざまな種類があり、材料それぞれにメリットとデメリットがあります。それを踏まえて、自分のライフスタイルに合った素材選びをしましょう。また、施工会社選びも重要。ZEHへの対応をひとつの目安に、断熱性の高い高性能な家を建てられる施工会社を探してみるのがいいですね。
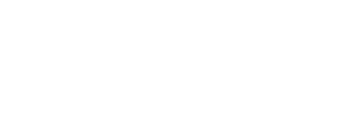
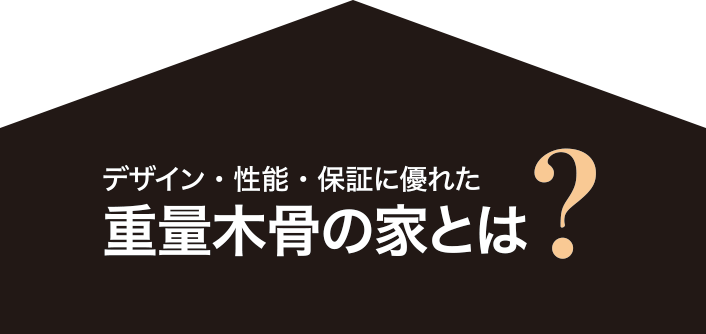







 はこちら
はこちら