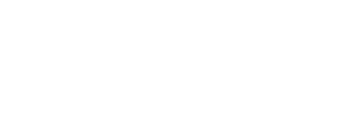家づくり対談
vol.3
対談場所は愛知県豊川市にあるkotoriのイベントスタジオ。
- 高倉潤(左)
- たかくらじゅん/FDM株式会社代表取締役。大学卒業後、東京都内で建築設計事務所を共同主宰。2015年4月にFDMに入社し、都内と大分の2拠点で設計活動を行う。2017年に大分県に帰郷し、FDM取締役副社長に就任。2021年から現職。
- 株式会社FDM
-
〒870-0839 大分県大分市金池南1-3-31
TEL 097-514-0007
従業員数:72人
創業:1973年
https://fdms.co.jp
- 今泉順次(右)
- いまいずみじゅんじ/株式会社kotori代表取締役。1977年愛知県新城市生まれ。地元ゼネコンおよび中堅ゼネコンに勤めた後、kotori一級建築士事務所設立。その後、株式会社kotori設立。
- 株式会社kotori
-
〒442-0857 愛知県豊川市八幡町亀ケ坪120-7
TEL 0533-75-6266
従業員数:5人
創業:2010年
https://www.kotori-5to6.com
第3回
kotori & FDM
これからの平屋について考えよう
核家族化が進み、部屋数を求められなくなった昨今、すべての空間をワンフロアに収めた平屋が人気と言われています。
今回は、愛知県を拠点とし、平屋を得意とするkotori代表取締役の今泉順次さんと、
住宅だけでなく非住宅も幅広く手がけている大分県のFDM代表取締役、高倉潤さんによる対談。
2人が口にしたのは、「平屋的な建て方」というユニークなキーワード。
そこには、これからの平屋のあり方と暮らし方のヒントがありました。
取材、文=植本絵美/写真=吉次史成
平屋をベースにした“平屋的な建て方”
―― kotoriもFDMも平屋を数多く手がけています。平屋に憧れる住み手が多いと思いますが、なぜ平屋は人気なのでしょうか?

今泉:暮らしやすさや、階段がなくスムーズに移動できること、掃除のしやすさ、バリアフリーなど、平屋のメリットはいろいろありますが、みなさん、どこかしら「平屋はぜいたくである」という考えがあって、憧れが強いのだと思います。
高倉:たとえば土地の面積で言うと、200㎡の土地で平屋に4人家族で住むと、一人当たり約50㎡も使えるので、マンションや2階建て、3階建てと比べると一人当たりの土地使用面積は平屋の方が圧倒的に広い。確かにそういう意味ではぜいたくではありますよね。平屋を建てようとすると、敷地に余裕が必要で、敷地面積は最低でも60坪はほしいところ。50坪でギリギリといったところでしょうか。
今泉:お客さんにまずお聞きするのは、「なぜ平屋にしたいのか?」ということ。敷地に余裕がなかったり、周囲の建物が近接するような立地で無理して平屋にすることはないと思いますし、平屋を選択する前に理由を考える必要があります。しかし理由を尋ねても、「平屋は良い」という漠然としたイメージで、具体的な理由がない場合が多いんですよ。

高倉:そうなんですよね。ヒアリングすると、最近は「老後のことを考えて、階段を上がり下がりしなくていい平屋にしたい」という理由の方が多い。「それなら、基本的な生活空間と主寝室は1階に集約して、子ども部屋や普段使わない部屋を2階に配置する平屋的な建て方はどうですか?」とご提案すると、ほとんどの方が「それ、いいですね!」と納得してくれます。
今泉:kotoriに来るお客さんも同じです。平屋を希望していても、結局は半分くらいのケースで一部を2階建てにしています。
高倉: 平屋をベースに一部を2階建て、あるいはロフトにした1.5階建てにした“平屋的な建て方”は1階に生活動線をまとめられ、2階はライフステージに合わせて子ども部屋、あるいは収納として使うなど、将来的にもフレキシブルに使えます。敷地面積や立地から平屋が難しい場合に非常に有効です。


吹き抜けのLDKは一部がロフト状になっている1.5階建ての平屋。敷地面積約495.87㎡、延べ床面積114.87㎡。
外部空間とつながる平屋の魅力
―― 平屋のメリットはたくさんありますが、一方で知っておくべきことはありますか。
高倉:平屋の最大の魅力は、なんと言っても庭など外部空間とのつながりですね。外部空間とつなげるには大開口が必要ですし、中と外をはっきりと分けるのではなく、中間領域をつくることで室内の魅力がさらに増します。

今泉:SE構法はスパンを飛ばせますし、平屋なら屋根も軽いから大開口をつくりやすい。大開口から日差しをとり入れることができ、SE構法と平屋、パッシブデザインは相性がいいと思いますね。
高倉:ウッドデッキは軒を深く出しておけば、雨の日にも使えるだけでなく、雨がかかりにくいことでメンテナンス性も高くなります。平屋はメンテナンス工事の際に足場を組む必要がなく、メンテナンスがしやすいというメリットもありますね。

屋外には室内と同じタイル張りのテラスがある。約482.52㎡、延べ床面積147.62㎡。
今泉:外構のことは後回しになりがちですが、庭のことも資金計画に含めておかないと、最後に予算がないということになってしまいます。ただ、現代は共働きのご夫婦が多いから、メンテナンスのことも考える必要があります。あと最近は、ドックランをつくりたいというお客さんも多いですね。
高倉:その一方で、平屋はプライバシーへの配慮が必要です。FDMが拠点にしている大分市は人口40万人ほどの地方都市ですが、都市部はマンションなどが建ち、住宅街も2階建てが建ち並んでいます。よほどの郊外でない限り、周囲に建物が近接するので、平屋だと周囲から丸見えになってしまう。そういった理由で、平屋だけど閉じてつくりたいという方は増えていますね。
今泉:その場合、中庭のプランは人気ですね。



平屋をベースにロフト、小屋裏、収納などを立体的に組みわせて空間全体を有効活用している。
家族のほど良い距離感をプランに反映させる
―― 平屋をプランする際、周囲からのプライバシーを守る工夫が大切とのことですが、他はどのようなことに配慮、工夫をしているのでしょうか?
今泉:平屋は外部からのプライバシーだけではなく、家族間においてのプライバシーも考えておかなければなりません。2階建てだと上下階でプライバシーを分けやすのですが、平屋は家族同士のプライバシーを確保しにくいので、プランで工夫する必要があります。
高倉:家族間の距離感は本当にそれぞれ。どういった距離感を心地よいと感じているのかによって、ゾーニングも大きく変わってきます。たとえば子ども部屋をどこに配置するのか。リビング横に置いて、子どもたちが帰ってきたらリビングを通るようにしたいというご両親もいますし、ある程度の年齢ならリビングを通らなくてすむ場所に配置したり。
今泉:お子さんが小さいのか、思春期なのか、年齢によって大きく変わってきますよね。子どもが小さい時は目が届く場所がいいけれど、思春期の子どもなら、それなりにプライバシーも必要になってきます。

先ほど中庭型プランが人気だと言いましたが、中庭を挟んで各部屋を配置すれば家族間の距離感も確保できますし、有効なプランなんです。
あと、見落としがちなのが、食洗機やガス洗濯乾燥機がある水回りと寝室の距離ですね。食洗機は夕食を食べた後、夜中に回すことが多く、その音が気になって寝られないという人も。平屋はそういったことにも配慮しておかなければいけません。
―― 平屋プランが単調になるようなことはないのでしょうか?
今泉:あえて高低差をつけた設計をすることもあります。「蒲郡の家」は3階建ての住宅が隣接していたため、中庭型のプランを採用しました。道路から敷地奥へと地面が1.5mほど高くなっていたことから、室内にも高低差をとり込み、床のレベルを3段階にしています。床に加えて天井にも段差をつけ、一つの建物のなかに多様な空間をつくることを目指しました。一室空間であったとしても、ちょっとした高低差で居心地や雰囲気が変わってくるんです。


敷地面積約306.95㎡、延べ床面積175.04㎡。
工務店として地域や職人を育てていきたい
―― お二人は、今後チャレンジしてみたいことはありますか?

高倉:大分には過疎や限界集落があり、街の商店街もシャッター通りだったり、空き家も多い。地元の人たちも空き家の活用方法を探っていても、資金もなく、なかなかビジネスが成立しにくい。僕ら工務店はそもそも地域のためにある存在なのに、そういった身近な人たちの助けになれてないんじゃないかと。地域にとっての工務店の存在意義とはなんだろう?とよく考えます。資金がなくても、工務店は手を動かしてモノをつくることができるのだから、必要最小限で空き家を修繕することはできるし、資金もクラウドファウンディングなど集める方法はある。ビジネスにならないからといってやらないのではなく、その状況を丸ごと受けとめるぐらいの気概で、地域のために何かできないか、探していきたいと思っています。

今泉:私は職人を育てたいですね。インドネシアが好きでよく行くのですが、インドネシアの人たちは親日家で、日本で職人として学びたい人がたくさんいるんですよ。彼らを職人として育てたら建設業界の人手不足にも貢献できるし、彼らがインドネシアに技術を持ち帰れば、インドネシアの発展にも寄与できる。だから、基礎から仕上げまで1人で切るような職人を育てたくて、その方法を模索中です。
高倉:職人を育てるのは重要ですよね。僕も、1人で複数の技術を身につける多能工の職人を育てる場をつくれないかと考えています。 大分県日田市は日田杉など木材が豊富な場所で、九州の中心に近いので、九州全域へのアクセスも悪くない。そういった場所に職人学校をつくれたらいいんじゃないかと。これからはどんどんAIが発達していき、AIに取って代わられる仕事もあるかと思いますが、手を動かす職人的な仕事はAIにはできないことなので、改めて見直され、価値が高まっていくと思っています。重量木骨のネットワークを使えば協業することも可能ですし、一緒に地域や業界を盛り上げていくことにチャレンジしていきたいですね。

―― お二人とも地域や業界というもっと広い視野で将来のことを考えておられ、非常に心強く、感銘を受けました。また「平屋的な建て方」という発想もユニークで、家族の在り方も多様化しているいま、これからの家づくりのヒントになると感じました。本日は興味深いお話をありがとうございました。