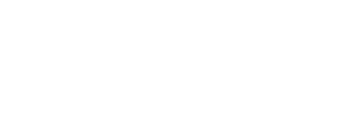プレミアムパートナー対談
vol.4
対談場所はじょぶのモデルハウス「北摂studio」
- 礒山哲也(左)
- いそやまてつや/株式会社じょぶ代表取締役社長。1998年じょぶ入社。2008年企画設計室を立ち上げて、自社で設計施工を始める。2013年じょぶ創業者から経営を引き継ぎ、代表取締役社長就任。
- 株式会社じょぶ
-
〒578-0911 大阪府東大阪市中新開2-10-26
TEL 072-966-9226
従業員数:15人
創業:1997年
https://job-homes.com/
- 髙木法(右)
- たかぎのりお/株式会社伊田工務店常務取締役兼最高経営責任者。ハウスメーカーを経て、2011年伊田工務店に入社し、設計部に所属。これまで390軒の住宅設計を手がけた。2019年より常務取締役就任、2025年より現職。
- IDA HOMES / IDA一級建築士事務所
-
〒657-0804 兵庫県神戸市灘区城内通4-7-25
TEL 078-861-1165
従業員数:22人
創業:1955年
https://www.idahomes.co.jp/
第4回
じょぶ & IDA HOMES
間取りについて考えよう
かつて間取りはnLDKで評価されがちでしたが、現代は暮らしが多様化し、
一人ひとりのライフスタイルに合わせた間取りが求められています。
今回の対談は、大阪を拠点とするじょぶ代表の礒山哲也さんと、神戸を拠点にする伊田工務店の髙木 法さん。
両社とも住み手の暮らしに寄り添った、ていねいな家づくりに定評があります。
二人とも口を揃えていうのは「間取りに正解はない」ということ。果たして、その真意とは―― 。
取材、文=植本絵美/写真=吉次史成
家は“買うもの”から一緒に“つくるもの”に
―― 家づくりに対してお客さんからの要望は時代とともに変化していますか?

礒山:以前は、家づくりの情報を得るには住宅展示場に行くのが一般的で、家はハウスメーカーなどから“買うもの”という認識だったように思います。しかし今は、ウェブサイトやSNSで情報を簡単に得られるようになり、住み手自らが主体的に考えて、家は一緒に“つくっていくもの”という認識に変わりつつあるように思いますね。
髙木:今は一般の方が得られる情報量が、以前とは比べ物にならないほど多いですよね。お施主様も新製品のことを調べていたりしますから、家づくりのプロである僕たちは常に情報をアップデートし、ニーズをしっかりと捉えていく必要があると思います。とはいえ要望通りにつくっても、良いものができるとは限りません。情報や要望の整理し、根底にある思いや背景に寄り添いながら、求めるものの先を提案することがプロの仕事だと思いますね。
礒山:時にはやらない方がいいこともあるので、その理由を説明し、説得する力も設計士には必要だと思いますよ。
―― 時代やニーズにともなって工務店も変わっている部分はありますか?

髙木:昔から地域や住み手の困りごとを解決していくという地域工務店の役割は変わってないと思います。ただ、お施主様がウェブで情報を簡単に得られるようになったことから、これまでのエリア外からの問い合わせが増えてきました。IDA HOMESは神戸エリアからの問い合わせが主でしたが、今は大阪や京都、時には東京からも問い合わせがあります。
礒山:以前の工務店は施工することが主な仕事でしたが、今は重量木骨のプレミアムパートナーのように、土地探しのサポートから資金計画、設計、施工、アフタフォローまで自社内ですべて解決でき、トータルで提案できる力のある工務店が増えてきました。ですから、家づくりの依頼先の選択肢が増えていると思いますね。




2階はオープンにつくっており、後から部屋を区切れるようプランしている。
間取りにはていねいなヒアリングが不可欠
髙木:ハウスメーカーの家は間取りがある程度決まっているので、それに住み手が合わせなければいけませんが、工務店の場合は住み手一人ひとりに間取りを合わせられる。間取りに暮らしを合わせるか、暮らしに間取りを合わせるか、アプローチが逆ですよね。お施主様はこれまでの暮らしでnLDKの間取りに合わせることが普通だと思っていると、家づくりも「こんなものか」と思ってしまいがち。本当は自分たちに合った間取りを手に入れることができるのに、「こんなものか」と思われるのは非常に残念です。ただ、住み手に寄り添った間取りを実現するには、細やかなヒアリングが必要になり、設計士の力量が試されます。
礒山:工務店の役割はまさにそこ! ライフスタイルが多様化しているからこそ、それぞれの住み手に寄り添えることができるのが工務店だと思いますね。間取りを考える時に、在来工法だと、どうしても耐震性を補うために壁や柱が増えてしまって設計が制限されてしまいますが、私たちが採用しているSE構法は「スケルトン・インフィル」の考えが基本なので、自由に間取りが考えられる。だからこそ、一人ひとりに合った間取りを実現できるわけです。
―― 現代はタイパや家事ラクなどが言われていますが、間取りにどのような影響を与えていますか?

礒山:じょぶが手がけるのは延べ床面積が30、40坪の家が多いのですが、端から端まで歩いても20歩程度で行けるわけです。そこで3歩分を減らすために、間取りを無理やり変えるのは、ちょっと違いますよね……。それならIoTをもっと駆使して、外からお風呂を沸かしたり、といった工夫をすればいいと思います。
髙木:僕も礒山さんも家事をしますから、家事のことをよく考えていますよね。タイパや家事ラクの工夫とは、住み手の生活に寄り添って整えていく細やかなこと。間取りに影響を及ぼすというより、ディテールなんです。
家は安心・安全であることが大前提
―― 今後、間取りはどのように変化していくと思いますか?
礒山:共働きのパワーカップルが増えていくでしょうから、キッチンだったら2人で立てる広さやプランするなど、細かなところは変化していくと思います。
髙木:奥さんが仕事で要職に就くと、家事との両立も難しくなるでしょう。収入に余裕があり、平日は外食やテイクアウトを利用するからキッチンはコンパクトでいいなど、生活のパターンが変わり、それに伴って家に対するニーズも変わってくると考えています。一方で、日当たりがいい場所にリビングを配置するといった、大事なことは変わらないと思いますね。変わるのはディテールの部分。将来を見据えてフレキシブルに対応はできるようには考えておきますが、それは間取りのディテールの部分です。
礒山:そう、家として大事なところはずっと変わらなくて、人が暮らすうえで家は安心・安全であることは大前提。内装などは暮らしや好みに関することはお客さんと一緒につくっていけばいいけれど、私たち工務店の大事な役割は耐震性や性能をしっかりと担保することです。

髙木:だから僕たちはSE構法を採用しているわけですよね。
礒山:2025年の4月に建築基準法の改正があり、基本的に木造住宅にも構造計算が義務付けられましたが、法改正があると、その対応にバタバタしがちですが、私たちはそれまでも構造計算することが当たり前だったから、対応に慌てることもありません。



地階がゲスト用の玄関とガレージ、1階が居住スペースになっている。
2階はすべての空間が外部テラスに面しており、大開口から豊かな緑を楽しめる。
工務店の枠を超えて、家づくりのことを考えたい
―― 最後に、今後はどのようなことに取り組んでみたいですか?
礒山:今後は、少子化や住宅の長寿命化に伴って住宅の新築は少なくなってくるので、将来的には建てた家のリフォームに対応できるように体制を整えておきたいですね。IDA HOMESさんとはお互いに現場を見学させてもらったりして行き来があるので、IDAさんが人手不足だったら自社の大工を派遣したり、逆に人材を供給してもらったり、といったことも取り組んでみたいと思います。
髙木:人手の確保は大切ですし、大工を社員として雇用する以上、仕事がない時があっても生活を支える責任があるので、工務店の枠を超えて人材を供給できるといいですよね。じょぶさんはチームワークが良くて、礒山さんはお施主様だけでなく、スタッフに対しても、どうすれば喜んでもらえるかをいつも考えている。その姿勢には学ぶことが多く、自分も見習いたいと思っています。
―― つい内装やデザインに目がいきがちですが、お二人がおっしゃる通り、家は安心・安全だからこそ、暮らしを楽しめるんですね。しっかりと安心・安全を担保してくれる工務店というパートナーを見つけることが非常に大事だと思いました。本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。