暖炉のある家の魅力を解説! 癒しの炎を暮らしに取り入れよう

暖炉のある家の魅力を解説! 癒しの炎を暮らしに取り入れようのインデックス
暖炉で心と体をあたためて、快適な冬を過ごしませんか。日本ではまだまだ暖炉のある家は一般的とは言えず、ハードルが高いと感じている方が多いのが現状。しかし、暖炉は意匠性の高さや、使い道の広さなど、さまざまな魅力に溢れており、新築を検討されている皆さんにぜひ導入していただきたいアイテムです。今回は暖炉の種類や特徴、設置時の注意点などについてまとめているので、家づくりの参考にしてみてくださいね。
暖炉とは

暖炉とは、レンガや石材などの耐火素材で建物と一体に作られた暖房器具のことを言います。通常、炉内で薪などの燃料を燃やし、直火の熱で暖を取り、煙は壁の中を通る煙突から外に排出されます。暖炉の起源は12世紀ヨーロッパで、この時代に2階建ての家が多く建てられるようになりましたが、室内で直接火を焚くと平屋よりも天井が低いため火災のリスクが高まり、耐火性に優れた暖房器具として暖炉が発明されました。
暖炉の種類
薪暖炉
薪暖炉は壁に埋め込まれた昔ながらのタイプ。扉が付いていないものがほとんどで、直火を楽しむことができます。レンガや石材などで作られているため重厚感があり、インテリアとしての役割も果たしています。暖炉本体がビルトインタイプであることに加え、煙突も壁の中に作られるため、後付けが難しく、導入をするなら新築時がおすすめです。
バイオエタノール暖炉
バイオエタノール暖炉は、トウモロコシやサトウキビなどの植物を発酵させて作ったバイオエタノールを燃料としています。バイオエタノールは燃やしても煙が出ないため、煙突を設置する必要がありません。また、一酸化炭素などの有害物質や臭いも出ないため、安全かつ快適に使用することができます。設置がしやすくデザインも豊富にあるため、暖炉の中でも特に人気のあるタイプです。
薪ストーブ
薪ストーブは熱効率が高く、暖炉の進化系にあたる暖房器具です。薪を燃料とする点が薪暖炉と共通していますが、薪ストーブは素材が鋳鉄や鋼板など金属製である点が大きな違いです。また、暖炉は直火で暖を取りますが、薪ストーブは金属製の本体を熱し、そこからの放射熱によって部屋を暖めます。
ガス暖炉
ガス暖炉はガスが燃料の暖炉で、薪に似せた擬木を炉内に置き、本物の薪が燃えているかのように演出します。煙突を設置する必要がなく、煙や煤が出ない点がメリット。スイッチ一つで火がつき、素早く部屋を暖められる点も魅力です。ただし、二酸化炭素が発生するため、換気は必要になります。
電気式暖炉
電気式暖炉は、電球の光で作り出された疑似炎によって、本物さながらの炎のゆらめきを再現します。この疑似炎は、リモコン操作で温度や明るさを調節することができ、季節やシーンに合わせた演出を可能にします。火を使わないため安全に使用することができ、煙突や燃料が不要であるため気軽に取り入れることができます。
暖炉のある家のメリット
癒し効果がある
暖炉のメリットの一つに、炎のゆらぎによる癒し効果が挙げられます。自然界には「1/fゆらぎ(エフぶんのいちゆらぎ)」と呼ばれる、不規則さと規則性が調和されたゆらぎの現象があり、人間はこのゆらぎに心地よさを感じ、癒されるそうです。また、暖炉には、薪が燃える音や香りなど、五感が刺激されることによるリラックス効果もあります。
インテリア性が高い
欧米では暖炉の焚き口を囲う部分に装飾を施すのが一般的で、このような暖炉装飾を「マントルピース」と呼びます。素材はレンガや石材、タイル、木材などさまざま。デザインに関しても、細かい彫刻を施したデコラティブなものからシンプルなものまで、豊富な種類があります。飾り棚のように使用し、写真や美術品などを置いて部屋を彩ることもできます。
直火で料理ができる
キャンプやバーベキューのように直火で料理を味わうことができる点も、暖炉のメリット。グリルや、煮込み、燻製など、さまざまな料理に対応でき、自宅にいながら気軽にアウトドア気分を楽しむことができます。家族みんなで火を囲みながら料理の出来上がりを待つ時間も、きっと楽しいものになるでしょう。
もしもの時の備えに
昔ながらの薪暖炉であれば、電気やガスを使わないため、災害でライフラインが絶たれた際に使用することができます。暖を取れるだけでなく、夜間の明かりとして使用したり、料理をしたりすることもできるため、緊急時に大いに役立ちます。先ほどお伝えした通り、炎には癒し効果もあるため、不安な夜の心強い支えとなるでしょう。
暖炉のある家のデメリット
コストがかかる
一般的な薪暖炉を設置する際、暖炉本体と煙突の費用を考慮しなくてはなりません。設置の初期費用は概ね100万円〜と考えておきましょう。これよりも安価に施工できるケースもありますが、耐久性を考えると、暖炉本体については30〜50万円、煙突については40〜80万円程度のものを選ぶ人が多いようです。また、薪暖炉は電気やガスなどの光熱費がかからない点が魅力ですが、薪を購入する場合はその分の費用もかかります。
メンテナンスが必要
薪暖炉は、使用しているうちに炉内や煙突に煤が溜まります。これを放置すると燃焼効率が悪くなり、暖房効果が下がってしまうだけでなく、最悪の場合は火災にもつながりかねません。このため、定期的なメンテナンスが必要になります。頻度は最低でも年に一回程度。プロの清掃業者に依頼する場合は、2万〜5万円が相場と言われています。
換気にも注意が必要
暖炉を使用する際は、薪を燃やすことによって一酸化炭素や二酸化炭素が排出されます。薪暖炉だけでなく、ガス暖炉やバイオエタノール暖炉を使用する際も発生するため、注意が必要です。1時間に1回程度は換気を行い、暖炉を使用し終わった後も火がついている場合は、煙突のダンパー(煙の流れを変えるパーツ)を開けておく必要があります。
後付けが難しい
暖炉は壁と一体型で作られ、煙突も壁の中を通るものが一般的です。後付けするのが困難であるため、暖炉を導入するなら、新築の設計段階から検討しておく必要があります。また、暖炉はどのようなタイプであれ、暖房効率や防火を考慮した間取りで配置する必要があるため、設計段階で暖炉中心のプランを練る必要があります。
暖炉を設置する際の注意点
火災や火傷
暖炉は直火を楽しむことができる反面、火災や火傷のリスクを十分に考慮する必要があります。暖炉の設置に関わる法令には、建築基準法や消防法、火災予防条例があり、天井や周囲に不燃性の内装材を使うなどの制限が定められています。これに加えて、火災リスクを下げるために暖炉の周りを片付けたり、幼いお子さんやペットが近寄らないように安全柵を設置したりするなどの対策も行いましょう。
ご近所トラブル
暖炉を使用する場合、煙突から排出された煙や臭いがご近所とのトラブルにつながることがあります。特に住宅密集地の場合は家同士の距離や風向きなどを考慮し、場合によっては煙突を必要としないタイプの暖炉を設けなければなりません。また、煙は薪が十分燃えていない時に発生するため、しっかりと乾燥した燃えやすい薪を使用する必要があります。
薪の保管
薪は風通しが良い場所に保管し、十分に乾燥させてから使用します。屋外に保管する場合は地面の上に直置きせず、薪棚を用意するなどして下からも風が通るように工夫しましょう。薪はよく乾燥したものでないと燃焼効率が下がり、煙が多く発生します。また、湿気が多いとカビや害虫、腐食にもつながるため、注意が必要です。
暖炉に使う薪の選び方
よく乾燥させる
先ほどからお伝えしている通り、暖炉に使う薪はよく乾燥させることが重要です。1〜2年かけてじっくりと乾燥させるのが理想で、適切に乾燥した薪は軽く、叩いたときに澄んだ音がするのが特徴です。また、薪を保管する際は、地面につかないように薪棚などで底上げし、風がよく通るように井桁状に積み上げましょう。
3種類の大きさを使い分ける
暖炉の温度や燃焼時間を調節するためには、3種類の大きさの薪を使い分けることがポイントになります。焚き付け用は直径約2cmの細い薪、長時間燃やす際は直径約10cmの太い薪が適切です。これに加え、直径約5cmの中くらいの薪を用意すれば、調節がしやすくなり、暖炉を快適に使用することができるでしょう。
広葉樹は火持ちが良い
広葉樹は針葉樹と比べて比重が大きく、火持ちが良いというメリットがあります。比重とは、水を1とした場合の同じ体積に対する重さのことで、比重が大きい広葉樹は重く硬いのが特徴です。代表的な種類には、ナラやカシ、クヌギなどがあり、燃焼時に高い熱量を発生させます。燃焼効率が高いため煙や煤の発生が少なく、暖炉や煙突のメンテナンス頻度を減らす効果も期待できます。
針葉樹は焚き付け用に
針葉樹は着火性が高く、焚き付け用の薪として非常に優れています。紅葉樹の薪に火を移す際に補助的に使用するのに適している一方で、燃焼が速く煙や煤の発生が多いため、長時間の使用には向いていません。代表的な種類には、スギやヒノキ、マツなどがあります。
暖炉のおしゃれな活用事例6選
暖炉がインテリアのアクセントに

こちらのリビングに設置されているバイオエタノール暖炉は、オーストラリアの人気ブランド「エコスマートファイヤー」。煙や煤が発生しないため煙突を設置する必要がなく、手軽に導入しやすいのが魅力です。明るいアースカラーを基調としたナチュラルなリビングの中で、暖炉の炎と薪が空間によく馴染んでいます。シンプルでありながらも、しっかりと存在感があり、インテリアのアクセントとして機能していますね。
柔らかな炎が出迎える玄関

家族が集まるリビングに設置されることの多い暖炉ですが、玄関に配置するのも良いアイデア。こちらの住宅では、玄関ホールの階段下にエタノール暖炉を設置し、柔らかく揺れる炎が家族や来客を温かく迎え入れてくれます。また、空間が白一色で統一されているため、炎の温かい色味がより一層際立っています。夕暮れになると左手の窓からライトアップされたシンボルツリーを望むことができ、暖炉の炎とともに幻想的な雰囲気を作り出します。
一日の疲れを癒す寝室の暖炉

寝室に置かれた、こちらのエタノール暖炉。スッキリと無駄のないデザインが特徴で、シンプルモダンな部屋によくマッチしています。また、暖炉全体が黒いため、炎との美しいコントラストがよく映えています。日中はハイサイドライトからの自然光にあふれた空間ですが、夜は暖炉の炎が部屋を優しく照らします。この暖炉によって足元からじんわりと体が温められ、一日の疲れも癒されることでしょう。
土間の暖炉はメンテナンスが簡単

こちらの事例では、ダイニングの片隅に土間スペースを設け、薪ストーブを配置しています。薪ストーブも調理に使用できるため、ダイニングやキッチンに近い間取りは何かと便利でしょう。また、土間は土足で使用する空間であるため汚れに強く、薪が燃えた後の煤や灰の掃除も簡単。タイル土間は蓄熱性も優れているため、薪ストーブの熱を地面に蓄え、部屋全体に効率よく行き渡らせることができます。
暖炉の明かりで空間をムーディーに

こちらもダイニングに暖炉を設けた事例。一見、レンガ造りの本格的な暖炉に見えますが、人気のエコスマートファイヤーを採用しています。バイオエタノール暖炉は臭いが発生しないため、ダイニングに特におすすめの暖炉タイプです。また、この暖炉は美しく安定した炎が特徴で、多灯照明と組み合わせることで、ムーディーな空間に演出することができます。大人な雰囲気が漂うこのダイニングでは、毎日のディナータイムが特別なひと時になることは間違いないでしょう。
自宅でバーベキュー気分を満喫

こちらの住宅には薪ストーブが設置されています。金属製の密閉された箱型の本体の中で火を起こすため、炉内では直火で調理ができ、熱くなった本体の上に鍋やフライパンを置いて加熱したり保温したりして使用することもできます。普段はあまり料理をしないという方でも、キャンプやバーベキューなどの野外調理であればやる気が出るという方もいらっしゃるでしょう。自宅にいながら、アウトドア気分で料理を楽しめることも暖炉の魅力です。
まとめ
暖炉の歴史は古く、昔から多くの人々に重宝されてきました。日本ではまだまだ一般的とは言えないものの、現代の暮らしに合った新しいタイプの商品も開発され、新たなファンを生み続けています。ただ、柔らかな炎に暖められ、五感で癒される点に関しては、昔も今も変わりません。新築のご購入を検討されている方は、この機会にぜひ、暖炉の導入も併せて検討されてみてはいかがでしょうか。
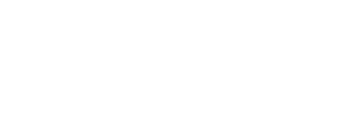
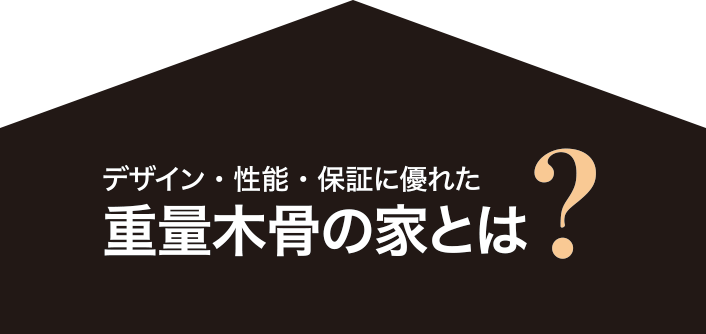











 はこちら
はこちら