吹き抜けのメリット・デメリット! 後悔しないためのポイントや間取りの注意点を解説

吹き抜けのメリット・デメリット! 後悔しないためのポイントや間取りの注意点を解説のインデックス
住まいに明るさと開放感をもたらす吹き抜け。上下のフロアをひと続きにした大胆な設計は機能性とデザイン性に優れ、多くの住宅に採用されています。しかし、吹き抜けにはメリットもあればデメリットもあり、その両方を知った上で検討する必要があるでしょう。おしゃれで快適な住まいを作るために、今回は吹き抜けの特徴や後悔しないためのポイントなどについてご紹介していきます。
吹き抜けとは

吹き抜けとは、上下複数階にまたがる連続した空間を指します。フロア間を隔てる天井や床をなくすことで天井が高くなり、縦方向への広がりを持たせることができます。一般的な戸建ての天井高は2.4m前後とされていますが、吹き抜けを作れば5m以上もの広々とした天井高を確保することができます。
吹き抜けのメリット
吹き抜けは縦長の構造ならではの様々なメリットがあります。また、そのメリットは窓を設けることでさらに効果を発揮します。
開放感がある
吹き抜けは上階と下階の区切りがないため、縦方向への広がりを感じることができます。吹き抜けで高くなった天井に窓を設ければ、視線がさらに遠く抜けていき、実際の広さ以上の開放感を感じることができるでしょう。敷地の広さに限りがある場合も空間を視覚的に広く見せることができるため、狭さや圧迫感を和らげることができます。
明るさを確保できる
吹き抜けの上部に窓を設ければ、高い位置から日光を取り込むことができ、照明に頼らなくても室内の隅々まで明るさを届けることができます。日中の電気使用量を節約できるため、環境にもお財布にも優しい設計と言えますね。また、室内が暗くなりがちな住宅密集地の場合も、隣接する建物に遮られることなく効率よく採光できます。
家族を身近に感じられる
吹き抜けによって上下階がひと続きの空間になるため、家族が別々のフロアにいても身近に感じることができます。声が届きやすいため、家族間のコミュニケーションも円滑になります。子育て世帯の場合は、家事や仕事をしていても子どもたちの様子がすぐに分かるため、安心して作業に取り組むことができるでしょう。
風通しがいい
吹き抜けには、立体的な空気循環を生み出し、風通しを良くするというメリットもあります。暖かい空気は上方向に流れていく性質があるため、縦に広い吹き抜け空間の中では上昇気流が発生しやすくなります。吹き抜けの上部と下部に窓を設ければ、下の窓から入った空気が上の窓から出て行き、自然な風の通り道を作ることができます。
吹き抜けのデメリット
吹き抜けにはメリットだけでなくデメリットもあります。デメリットとその対処法を知った上で、吹き抜けを検討してみてくださいね。
冷暖房効率の低下
吹き抜けは空間が広々としているため、エアコンの効きが悪くなってしまうというデメリットがあります。また、吹き抜けは自然な空気循環を生みやすい一方で、冬場はエアコンの暖気が下階に留まらず、室内が温まりにくくなってしまうことがあります。部屋全体を効率よく温めるには、天井にシーリングファンを設置して室温のムラをなくすという方法もあります。
外部からの視線が気になる
吹き抜けは住宅密集地でも採光しやすいというメリットがありますが、窓の大きさに注意が必要です。窓が大きいと日光をたくさん取り込むことができ、視覚的にも広さを感じやすくなりますが、隣家から家の中が見えやすくなってしまうというデメリットがあります。カーテンやルーバー、あるいは植栽などで目隠しするなどの工夫が必要になります。
音やにおいが広がりやすい
上下階がつながっているため、音やにおいが広がりやすいという側面もあります。音に関しては、寝室や書斎など、静かさを必要とする部屋は、吹き抜けに面した間取りに配置しないことをおすすめします。また、これらの部屋には防音壁を採用しましょう。においに関しては換気扇を回したり、こまめに窓を開けて自然換気を行ったりしましょう。特ににおいの発生しやすいキッチンには、性能の良いレンジフードを設置しましょう。
メンテナンスしづらい
吹抜けは高さがあるため、メンテナンスしづらいというデメリットも。吹き抜けは2階分以上の天井高があるため、脚立などを使って掃除をする場合は怪我のリスクが高くなってしまいます。業者に頼むのが最も安全で確実な方法ですが、もっと手軽に済ませたいという方は、吹き抜け掃除用の柄の長いモップやワイパーなどもあるので、ぜひ使ってみてくださいね。
吹き抜けと相性の良い間取り
吹き抜けのある家を建てたいと考えているものの、どこに吹き抜けを設けたら良いのか迷われている方も多いのではないでしょうか。ここでは吹き抜けと相性の良い間取りについてご紹介していきます。
リビング
リビングは家族だんらんの空間であるため、居心地の良い場所である必要があります。吹き抜けを作れば広々と快適な空間にできるだけでなく、リビングでくつろぐ家族と、別の階で活動する家族がつながりやすくなります。また、吹き抜けのリビングに階段を作れば、家族が必ずリビングを通る動線を作ることができ、家族が顔を合わせやすくなります。
玄関ホール
玄関はお客さんを最初に迎え入れる大事な場所であり、玄関が与える印象が家主のイメージに直結すると言っても過言ではありません。吹き抜けを作れば、明るく開放的な玄関になり、デザイン面でも個性を出すことができるため、訪れた人たちに良い印象を残すことができるのではないでしょうか。
廊下
吹き抜けに面して廊下を設ける造りもおすすめです。廊下の両側に壁があると圧迫感や閉塞感を感じやすいものですが、吹き抜けに面していれば視界が開けて開放感を感じることができます。廊下のスペースを少し広めに取ってカウンターを設ければ、明るく広々とした空間で勉強したり読書したりすることができます。
吹き抜けで後悔しないためのポイント
吹き抜けを作って後悔したという声は、残念ながら少なくありません。しかし、失敗しやすいポイントをあらかじめ知っておくことで、後悔のない吹き抜け空間を作ることができます。
耐震性の高い構造にする
吹き抜けの空間が広ければ広いほど、耐震性は下がってしまいます。しかし、せっかく吹き抜けを作るなら広々と快適な空間にしたいものです。高い耐震性を保ちながら、自由な空間デザインを可能にする手段の一つに「SE構法」という木造建築技術があります。高強度の集成材を特別な金物で接合することで、構造強度を保つことができ、地震に強く、おしゃれな吹き抜け空間を作ることができます。
空気循環設備を設ける
吹き抜けを作る際には、シーリングファンやサーキュレーターといった空気循環設備を設けると良いでしょう。シーリングファンは天井に取り付ける大型送風機のことで、羽を回転させて室温のムラをなくします。夏場は冷房使用時に足元に溜まる冷気を循環させ、冬場は上部に集まった暖気を下部に送り返して室内全体を快適な温度に保ちます。
サーキュレーターは置き型の送風機で、家を建てた後に購入することが可能です。シーリングファンと同様に空気循環を生み出し、室温を均一にします。
直射日光を防げるようにする
吹き抜けは明るさを確保できる一方で、直射日光に注意が必要です。このため、カーテンやブラインド、ロールスクリーンなどで日射量を調節できるようにしましょう。紐を引っ張って開閉できるタイプであれば、地面に足をつけたまま、高所のカーテンを開け閉めすることができます。また、電動のものを取り入れればリモコンで操作できるため便利です。
家の断熱性・気密性を高める
吹き抜け空間の冷暖房効率を高めるには、断熱性や気密性を高める必要があります。断熱性や気密性が低いと、外気の影響を受けやすくなり、せっかくエアコンで室温を調節しても部屋が温まらなかったり、涼しくならなかったりしてしまいます。また、窓を設ける際にも断熱性と遮熱性を持つガラスを使用するようにしましょう。
吹き抜け空間をおしゃれに見せるコツ
吹き抜けを作るだけでも、十分おしゃれな空間にすることができますが、内装の工夫によって、よりデザイン性の高い空間に演出することができます。
梁を見せる
吹き抜けは空間を広く見せられるのがメリットですが、その一方で間延びした印象になってしまうことも。梁を見せれば、空間を引き締め、ダイナミックに演出することができます。また、見た目の印象を良くするだけでなく、構造の強度を高められる点も魅力です。梁の上部にほこりが溜まるのが気になるという方は、梁と天井をピッタリとくっつける設計がおすすめです。
家具を吊るす
天井や壁、梁に家具や雑貨を吊るせば、吹き抜けの広い空間を立体的に彩ることができます。天井を見上げた時にお気に入りのアイテムが目に入れば、視覚的な楽しさがプラスされ、吹き抜け空間がより居心地の良いものとなるでしょう。観葉植物やハンモックを吊るして癒しの空間を作ったり、ブランコを設置して子どもたちが遊べるようにしたり、吊るすアイテム次第でさまざまな楽しみ方ができます。
勾配天井にする
勾配天井は一般的な平天井よりもさらに高さをつけることができ、より大胆な吹き抜け空間を作ることができます。通常の吹き抜け以上に広々とした空間を作ることができるため、明るさや開放感といった吹き抜けのメリットを最大限に生かすことができます。また、天井が傾斜しているため、個性的なデザインの空間を作ることができます。
スケルトン階段にする
スケルトン階段(ストリップ階段)とは、足を乗せる踏み板と骨組みのみで作られた階段のことを指します。光や風を通す軽やかなデザインであるため、これを取り入れることによって、インテリア性の高い部屋を作ることができます。採光や通風の邪魔をせず、圧迫感を感じさせないため、吹き抜けの空間に取り入れても違和感なく馴染ませることができます。
照明を工夫する
吹き抜け空間をおしゃれに見せるには、照明計画も欠かせません。光の反射や影を利用することで、空間を表情豊かに演出し、吹き抜けの立体感をさらに引き立てることができます。また、照明を空間のアクセントにしたい場合はシャンデリアやペンダントライトなど、視覚的に楽しめるデザインの照明がおすすめ。
吹き抜けの開放感を邪魔することなく照らしたい場合は、ダウンライトなどのスッキリとしたデザインの照明を取り入れましょう。また、柔らかく幻想的な間接照明を取り入れて、ムーディーな空間に仕上げても良いでしょう。
吹き抜けの事例が豊富な重量木骨の家
開放的なイメージから大変人気のある吹き抜け。憧れの吹き抜けは、さまざまな生かし方があります。暮らしがさらに豊かになるような吹き抜けの取り入れ方を「重量木骨の家」の数多くある実例からご紹介します。
複数の大窓から光を取り込むLDK
こちらは2階のLDKに設けられた吹き抜け。大きな窓が複数設けられ、光をたっぷりと取り込んだ明るく開放的な空間になっています。また、内装は白を基調とし、アルミサッシやスケルトン階段の鉄骨の黒が空間を引き締めています。吹き抜けの上には子供部屋が設けられていて、異なるフロアにいても窓越しにコミュニケーションを取ることができます。
狭さを感じさせない狭小住宅
南北に長い狭小地に建てられたこちらのお住まい。細長い吹き抜けを採用することで、家の狭さを感じさせない造りになっています。この吹き抜けは中庭に面していて、上部に設けられた窓から自然光を取り込めるようになっています。また、吹き抜けに面した壁には造作の壁面収納があり、空間を無駄なく活用しています。
柔らかなカーブを描く吹き抜け
柔らかなカーブを描いた吹き抜けのデザインが印象的なリビング。吹き抜けの上下に大きな窓が設けられ、室内全体に太陽光を取り込んでいます。また、吹き抜けに面して中庭が設けられていて、横方向にも広がりを感じられます。リビングのすぐ上のスペースはオーナー様の書斎コーナーになっていて、一人の時間を楽しみながらも家族の気配を感じられます。
遊び心のあるボルダリング壁
こちらの事例では、2階から3階の吹き抜けを利用してボルダリング壁を設けています。白を基調とした開放的な空間の中で、色とりどりの取手が見た目のアクセントになっています。子どもはもちろん、大人も楽しむことができ、ボルダリングを通して家族がコミュニケーションを取れるようになっています。
まとめ
吹き抜けは広々とした空間設計によって、採光や通風などさまざまなメリットを住まいにもたらします。一方で、熱効率やメンテナンスなどの面でデメリットがあるということについてもお伝えしました。今回ご紹介した内容を踏まえて事前にしっかりと対策し、ぜひ理想の吹き抜け空間を作ってみてくださいね。
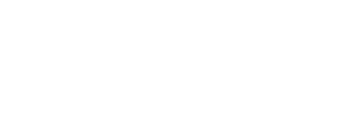
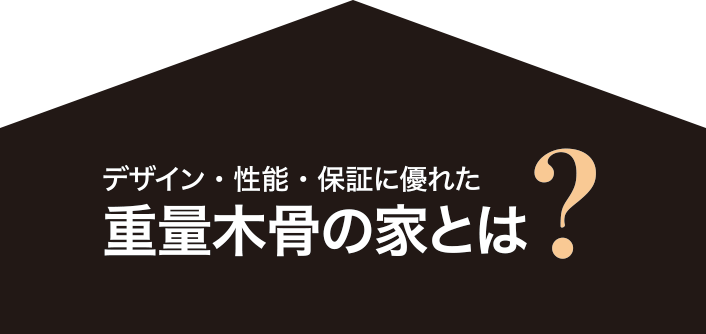
























 はこちら
はこちら