「ウッドデッキ」が、プラスアルファの「楽しい暮らし」を実現する

「ウッドデッキ」が、プラスアルファの「楽しい暮らし」を実現するのインデックス
近年とても人気の高いアイテムが「ウッドデッキ」です。このウッドデッキを上手に活用して、暮らしに楽しさや気持ちよさをプラスされるような家づくりに取り組んでみましょう。
1. ウッドデッキの魅力とは
最近増えているウッドデッキですが、その存在価値は一体どんなところにあるのでしょうか。単なる洗濯物を干す場所や、家の中では邪魔なものを置く場所としてだけなら、それほど魅力的なものではありません。
ここで考えるウッドデッキの魅力とは、その暮らしの中でワクワクするようなライフスタイルを実現できるツールとしての役割を果たせることです。
今回はそこを詳しく解説していきます。
1-1. 「もうひとつのリビング空間となる」
家づくりを考えるときに、「最もこだわる空間はどこですか?」と聞かれたら、多くの人が「リビング」と答えるのではないでしょうか。その大きな理由は、リビングは一番家族が集まる場所であり、最も広くて落ち着ける場所となるからです。
LDKと呼ばれるリビング・ダイニング・キッチンがつながっている場合は、特にその傾向が強くなります。料理をしたり、食事をしたり、TVや音楽を楽しんだり…と、多くの人にとって暮らしの中心となっているのです。また、家族や友人とのコミュニケーションの大事な場所でもあります。家づくりでリビングを考えるとき、それらのたくさんの楽しい暮らしをイメージしながら計画を進めていくはずだと思います。
「ウッドデッキ」には、これらのような「もうひとつのリビング空間」としての役割を果たしてくれます。「リビング」が二つになると言っても決してオーバーな表現ではありません。
「週末は家族で朝食を」「気の置けない友人達との午後のティータイム」「夏の夜はビールを飲みながら夕涼み」…などなど。
ウッドデッキはいつでも、リビングに変わる「楽しいライフスタイルを実現する空間」となりうるのです。
1-2. 「アウトドアとしての楽しみ」
家の外だからこそできる楽しみ方も、ウッドデッキの大きな魅力です。その代表が「BBQ(バーべキュー)」でしょう。天気の良い日に、家族や友人たちとワイワイとおしゃべりしながら、その場で焼いたお肉や野菜を食べるのはとても楽しいイベントです。
家の中では難しい、煙や匂いが出るような料理でも、外のウッドデッキなら気兼ねなくトライできます。また、小さなお子さんがいる家庭では、簡単にビニールプールで水遊びも楽しむことができます。
最近流行りの「ハンモックでお昼寝」も気持ちよさそうですよね。わざわざ山や川に出かけなくてもアウトドアライフが気軽に楽しめるというわけです。
1-3. 「リビングが広くなる」
いっそのこと「リビング」も「ウッドデッキ」も一つの空間として考えてしまおうということです。
リビングの床は木のフローリングを採用することが多いと思いますが、ウッドデッキにも床に木材を使っているので、「リビング」と「ウッドデッキ」が一つの空間としてのつながりを感じることができます。
床の材種や貼り方向へレベル差を工夫すれば、まるでリビングが外まで広がっているような感覚になります。更にリビングに大きな開口窓を採用すれば、このつながり感はとても大きくなります。
室内のリビングを広くすると建築費用が大きく増えてしまいますが、ウッドデッキはその5~6分の1以下のコストで造れます。実はコストパフォーマンス的にもとても魅力的なのです。
1-4. DIYが可能
最近は材料を自分で購入して、DIYでつくるという方も増えています。ホームセンターにはそんな人たちに向けた材料や道具も豊富に揃っています。また、専用の書籍はもちろんのこと、YouTubeなどには楽しいDIYの動画も数多く投稿されていますので、ご興味ある方は一度検討してはいかがでしょうか。
大工さんに頼むより手間はかかりますが、コストは安くできます。そして何より手の掛かった分だけ、長く愛着を持って使えると思いますよ。
2.ウッドデッキの注意点
2-1. 「メンテナンスについて」
ウッドデッキは家の外にあるのでどうしても自然の風雨の影響をうけやすく、耐久性を考慮しなければいけません。つまり「メンテナンス」のことをしっかりと考えて計画をすることが重要になります。
そこでのポイントは、ウッドデッキ材として使用する材木の種類の選択です。この選択をイニシャルコストだけでなく、将来のメンテナンスのことも考えて決定するということですね。
デッキ材には「天然木」と「人工木」の2種類があります。
樹脂などで人工的に造られた「人工木」であれば腐ることはないので、ほぼメンテナンスの心配はありません。しかしながら、あくまでも人工の木なので本来の自然素材の風合いがないことが大きな欠点です。
天然木については「ソフトウッド」と「ハードウッド」と分かれます。「ソフトウッド」の中でも「SPF」のように耐久性の低いものから、比較的耐久性の高い「レッドシダー」などもあるので、メンテナンスの度合いによって選んでください。いずれにしても数年に1回は塗装などのメンテナンスが必要です。これらの利点は木質感を感じる素材ながら安価であることです。軽くて柔らかいので、DIYには向いている木材です。
対して、「イぺ」や「ウリン」、「セランガンバツー」などの「ハードウッド」は、重くて硬い素材であり、耐久性も高いのでメンテナンス性に優れています。デメリットは高価であることですが、長い目で見たらお得感を感じる方もいるかもしれません。
いずれにしても、「自分で手をかけること自体も楽しんでいきたい」のか、「できるだけメンテナンスフリーにしたい」のか、それぞれのライフスタイルの考え方で決めていただければと思います。
2-2. 「建物の構造の強さでより魅力的な空間になる」
ウッドデッキは家の外にあるものなので「建物とは関係ない」と思いがちです。しかし、そんなことはありません。この魅力を最大に引き出すためには、実は建物の構造が大きく関係するのです。
まず、ウッドデッキとリビングをつなぐ窓は、大きな開口であればあるほどつながり感や開放感を感じると先に述べました。しかしこの大きな開口窓を実現するためには、地震時に必要な耐力壁を減らさなければいけないことになります。
壁だけに構造を頼っている在来木造や2×4では大きな開口窓を設計すると、その結果、耐震性を大きく落としてしまうことになり、本末転倒ということになります。
それは、「SE構法」のような柱と梁でも耐力を持つラーメン構造を採用することで解決できます。その結果、耐震性を落とさずに大きな開口部が可能となり、ウッドデッキとリビングの開放的なつながりも実現できるというわけです。
また、都市部などでは「2階リビング+ウッドデッキルーフバルコニー」や「屋上ウッドデッキバルコニー」というパターンも多いと思います。ここでも、屋上などに荷重をかけても安心の「構造計算」をすることが大事になるのです。

2-3. 外からの視線を考える
ウッドデッキは外で楽しむ空間です。そこで眺望をどう考えるかが重要なテーマとなります。建築地が景色の良い場所であれば、それらの眺めを楽しめるように配置することを考えるでしょう。
一方、都市部や前面に交通量の多い道路などがある場合、外からの視線が気になってゆっくりと楽しめないというケースもあります。
対策としては、ウッドフェンスを設置したり、中庭のような設計にして、外からの視線が隠れる場所にウッドデッキを配置したりということがあります。
いずれにしても、その敷地条件に最適な計画で進めるということが大切です。
このようによく考えられたウッドデッキは、新しい暮らしに「楽しさ」や「憩い」をたくさんプラスしてくれます。ぜひ、皆さんも楽しいウッドデッキライフを実現してください!
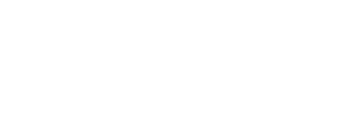
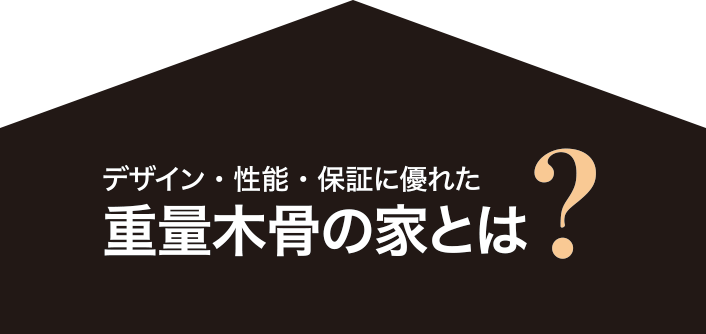









 はこちら
はこちら