【実例紹介】長期優良住宅の建て方ポイント解説

【実例紹介】長期優良住宅の建て方ポイント解説のインデックス
家を建てるなら「長期優良住宅」で、とお考えの方の方も多くなってきました。一生もののお買い物ですので、より良い家を、安心の住まいを、と希望するのも当然のことです。では、何を基準に長期優良住宅とされ、長期優良住宅にすることでどんなメリットを享受できるのでしょうか。それは本当にあなたにとっての良い家なのでしょうか。
これから家づくりにとりかかる方に、長期優良住宅の基準と、そのメリット・デメリットなどを解説いたします。
1.長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、その名のとおり、「長く安心して住まうことのできる家」「将来までをも見越した家」のことです。これらは漠然とした概念ではなく、明確な基準があります。
・数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(少なくとも100年程度)
・極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
・居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
・必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
・建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
―などです(長期優良住宅の認定基準(概要)│国土交通省)。
1-1.数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
家を長きに渡り使用するためには、その家の構造がしっかりしていること、そして定期的に行うメンテナンスが容易に出来なければなりません。このため、鉄筋コンクリート造ならばコンクリートが充分な厚みであること、木造であれば床下の空間を充分に点検出来るだけの高さと点検口を持っていることが必要です。
1-2.地震が起きた際に行う補修が容易で、損傷レベルを低くすること
地震大国ともいわれる日本で、家が損傷・倒壊しないためには、「耐力」に注目しなければなりません。耐震基準は、1924年の東海大地震を機に施行され、1968年の十勝沖地震、1981年には宮城県沖地震、2000年には阪神・淡路大震災といった大きな地震の度に見直されてきました。
2017年現在、「新耐震設計基準(新耐震とも呼ぶ)」を満たせば家を建てることができますが、長期優良住宅では、この建築基準法の1.25倍以上という基準が求められております。
1-3.ライフスタイルの変化に対応するため、間取りの変更が可能な措置
次の世代にまで引き継げる家には、強さだけでなく、家族構成・年齢の変化に応じて間取りを変化できる柔軟性も必要です。たとえば、親が自宅での介護を希望したときには、段差をなくしたり、車椅子で生活できるためのバリアフリー改修を行う必要があるでしょう。それに伴っては、廊下を広げる、住宅用エレベーターを取り入れるなどの大掛かりなリフォームが必要です。
このような大規模なリフォームは、家そのもの(躯体)の強度が重要です。家は、柱や壁で2~3階の重量を支えています。耐力が不足すると、上のような大掛かりなリフォームできないこともあるのです。
1-4.断熱性能等の省エネルギー性能の確保
私たちの生活は、地球の自然環境に支えられています。せっかく建てる家ならば、エコロジーとエコノミーの両方の観点でよい家を建てたいものです。また、大きなお金を動かして我が家を手に入れるのですから、冬は暖かく、夏は涼しい家を実現し、可能な限り電力に頼らない暮らしをしたいものです。
長期優良住宅における省エネ基準は、「UA値」という数値で表現され、地域ごとにその基準値が定められています。UA値とは、外皮平均熱貫流率とも呼ばれ、その値が低ければ低いほど断熱性能が高いことを表しています。
1-5. 定期的な点検・補修等に関する計画の策定
長期にわたって「家の健康」を保持するためには、定期的なメンテナンスが必須です。そして、そのメンテナンスも計画的に行わなければなりません。
特に重要なのが、構造耐力面で主要な部分、雨水侵入を防止すべき部分、設備の維持管理と点検です。これらを最低でも10年ごとに点検する計画を立て、実施することが求められています。
2.長期優良住宅で減税や金利優遇等、金銭的メリット
長期優良住宅は、「子や孫の代まで残る家」という大きなメリットがあります。しかしながらそれだけではなく、他の面でもメリットを享受できます。
2-1.住宅ローン控除が優遇される
マイホームを取得するにあたって気になるのが住宅ローン控除(減税)です。2017年現在、一般的な住宅は、控除対象借入限度額4,000万円、最大控除額400万円、年間での控除認定額が40万円です。
それに対し、長期優良住宅であれば、控除対象借入限度額5,000万円、最大控除額500万円、年間での控除額が50万円に拡大されます。
2-2.所得税の減税
もしも住宅ローンを利用していなくても受けられるのが、「長期優良住宅の投資型減税」です。控除対象限度額は650万円で1年間、最大控除額は65万円です。もしも控除額より大きな額となれば、翌年分の所得税からも控除されます。
2-3.住宅ローンの金利優遇
長期優良住宅は、住宅ローンの金利を安く抑えることも可能です。2017年現在、全期間固定金利で知られる「フラット35S(金利Aプラン)」が利用でき、フラット35と比較して、借入当初10年間は0.3%低くなります(【フラット35】Sとは│住宅金融支援機構)。また、その他に、自治体と提携した金融機関でローンを利用するときにも優遇金利が適用されることがあります(「ふくおか型長期優良住宅」推進プロジェクト!│福岡県)。
3.長期優良住宅を建てるに当たって考えられるデメリット
長く住まえるどっしりとした良い家が長期優良住宅です。メリットばかりではありますが、あえてデメリットを挙げるとしたのなら以下の事柄です。
3-1.申請のコスト
長期優良住宅を建て、税金や住宅ローンの金利面でメリットを得ようとする際、「認定」を受ける必要があります。これに必要な住宅性能評価機関の技術的審査に5万円前後の費用が必要です。また、自治体に認定を求めるときにも数千円の費用が必要です。
これらには書類や検査が必要で、建築を依頼する建築会社・工務店が手続きをしてくれますが、その分コストが上乗せされます。
3-2.長期優良住宅に慣れた建築会社・工務店選び
長期優良住宅の制度の施工年は、2006年のことです。良い家をつくり、手入れをしながら大切にするという理念の下スタートした制度ですが、やっと数年が経過したところです。まだ長期優良住宅について慣れていない建築会社や工務店も少なくありません。
長期優良住宅と認められるには、複合的な条件をすべてクリアする必要がありますので、建築実績の豊富な会社を選ばなくてはなりません。スムーズに家づくりをするためにも、必須項目です。
3-3.建築費用そのものが高くなりがち
より良い家という位置づけの長期優良住宅ですので、建築費用が高くなってしまうのは当然のことです。しかし、子や孫の代まで家を受け継ぐ事を前提に考えて、トータルコストで考えれば、初期投資する価値はあるのではないでしょうか。また家の売却という選択になった時も、一般的な中古住宅と比較すると有利になることは多いでしょう。
【実例紹介】長期優良住宅の重量木骨の家施工例紹介
長く子や孫の代まで引き継いでいける長期優良住宅は、環境にやさしいものです。さらに日本で古来から続く、「受け継ぐ家」という概念にも沿ったものです。
重要なポイントは「強度」「手入れのしやすさ」です。私たちの作る重量木骨の家は、まさしくこの受け継ぐ家にふさわしいものですし、長期優良住宅も多く取り扱っています。
長期優良住宅として建てられた家をご覧ください。子・孫にも継いでいってもらうための工夫も凝らしています。
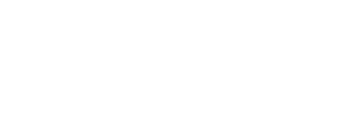
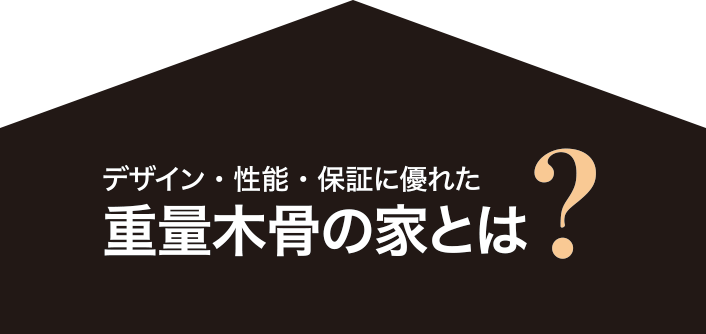











 はこちら
はこちら