木の家で暮らしに潤いを。癒しと温もりの家づくりのポイントを紹介

木の家で暮らしに潤いを。癒しと温もりの家づくりのポイントを紹介のインデックス
美しい木目に、爽やかな香り、そして、さらりとした肌触り……。木材を使って建てる「木の家」は、住む人に癒しと安らぎを与え、機能性にも優れた住宅と言えます。今回の記事では、木の家の特徴や、木材の種類や使い方のコツなどについて解説していきます。おしゃれで居心地の良い家づくりの参考にしてみてくださいね。
木の家とは?
「木の家」と一口に言っても、その定義はさまざま。日本の一般的な木造住宅を木の家と呼ぶ場合もあれば、ヒノキやスギなどの天然木を使って建てた家のみを指す場合もあります。ここでは、住宅の構成要素である「構造体」「内装」「外装」に木材が使われている家について解説していきます。
構造体が木の家
構造体が木でできている木造住宅は、木の家の一種です。木造住宅にもいくつか種類があり、例えば、日本で古くから用いられている「木造軸組工法(在来工法)」は、柱・梁・筋交いを組み合わせて建物を支える構造が特徴です。このほかにも、強固な六面体構造の「枠組工法(ツーバイフォー工法)」や、梁や柱を金物やボルトで強力に接合する「木造ラーメン工法」、丸太を積み上げて作る「ログハウス」などの工法があります。
内装が木の家
構造体だけでなく、内装に木が使われている家も木の家と呼ばれます。内装材として使う木材は、床や、壁面、天井など、あらゆる箇所に用いることができます。また、構造の梁や柱を現しにしたり、木製家具を揃えたりすれば、木の温もりをより感じられる癒しの空間をつくることができます。
外装が木の家
外装材に木を用いて、ウッディな外観に仕上げた住宅も木の家に当てはまります。外装が木の家を作るには、外壁を板張りにしたり、ドアを木製にしたりするなどの方法があります。木の外装は、外気にさらされることによって、年を重ねるごとに色味や風合いが変わっていきます。長く住むことで、このような経年変化を楽しめるのも、木の家の魅力の一つです。
木の家に使われる木材
木の家に使われる木材には、いくつかの種類があります。それぞれの機能性や注意点を比べてみてくださいね。
無垢材
無垢材とは、天然木から切り出した一枚板のことを言います。木目の美しさや、香り、肌触りなどが魅力で本物志向の方におすすめの木材ですが、コストが高くなるというデメリットも。傷がつきやすく、また、湿度や温度によって反りや木割れなどの変形が起こりやすい点にも注意が必要です。
挽板
挽板は、天然木を2〜3ミリ程度に薄くスライスし、合板の表面に貼り付けたもの。表面材として十分な厚みがあるため、無垢材のような天然の質感を感じられる点がメリットですが、同様に湿度や温度による伸縮が起こりやすいというデメリットもあります。
突板
突板もまた、天然木を薄くスライスし、合板の表面に貼り付けたもの。スライスの厚さは挽板よりもさらに薄く、0.2〜0.3ミリ程度です。合板の割合が高いため扱いやすく、低コストな点が魅力。しかし、表面材としては薄いため、触り心地が硬いというデメリットがあります。
シート材
木目を印刷したシートを表面材として合板に貼り付けたもの。天然木を一切使わず紙や樹脂フィルムなどに印刷しているため、コストを抑えることができ、柄や色味のラインナップも豊富です。ただ、天然木と比べると、木ならではの温かな質感は感じられません。
集成材
小さく切った木の板を結合して作られた木材のこと。安定した品質や強度の高さが特徴で、無垢材よりも反りや歪みが少なく、使い勝手が良い点がメリットと言えます。家の柱や土台に使われるものは、構造用集成材と呼ばれています。
木の家の機能的なメリット
木の家の魅力は、見た目の美しさだけではありません。木材、特に天然木をふんだんに使うことにより、機能的なメリットを享受することができます。
調湿性
木材には、室内の湿度を一定に保つ効果があります。蒸し暑い夏は湿気を吸収し、冬の乾燥した時期には水分を放出するため、木の家はまさに、日本の気候に最も適した住宅と言えるでしょう。また、調湿効果によってカビやダニの発生も抑制するため、快適で清潔な住環境を維持することができます。
断熱性
木材は熱を伝えにくい性質があるため、夏は外部の熱を遮断し、冬は室内の暖かさを逃がさず、年間を通して室温を安定させることができます。床や壁、天井など、家のあらゆる箇所に無垢材を用いれば、その効果はより発揮されるでしょう。また、家の冷暖房費が緩和されるため、光熱費の節約にも繋がります。
衝撃吸収性
木材には衝撃を吸収する性質があります。木材は小さなパイプ状の細胞でできていて、このパイプが柔軟に変形することでクッションのような役割を担います。怪我の衝撃を緩和するだけでなく、歩行時のわずかな衝撃も和らげ、足腰への日常的な負担を軽減します。高齢者や小さな子供がいる家庭では特に重要な特性と言えるでしょう。
リフレッシュ効果
木材には「フィットンチッド」という成分が含まれています。この成分は、ストレスやアレルギーを緩和したり、免疫力を高めたりする効果があるとされています。木の家の独特の温もりと芳香はこの成分によるもので、家の中にいながら、まるで森林浴に行ったかのように気分をリフレッシュさせることができます。
木の家の注意点
木の家にはさまざまなメリットがありますが、注意しなくてはならない点もあります。木の家を建てる際は、以下のことを踏まえる必要があります。
変形や損傷
木材の中でも無垢材は特に、湿度や温度の変化によって伸縮が起こりやすく、このため、反りや亀裂などの変形が生じやすいというデメリットがあります。また、表面が柔らかく傷がつきやすいため、扱いには注意が必要です。合板は無垢材よりも伸縮しにくく、耐久性がありますが、ワックスがけなどの定期的なメンテナンスは欠かせません。
腐食
木材は、湿気や水分に長期間さらされると腐食してしまうことがあります。特に、水回りや床下、外壁などは要注意。腐食は建物の構造強度を弱め、最悪の場合は倒壊につながる可能性もあります。これを防ぐためには、防水処理や換気を適切に行うことが不可欠。定期的に点検を行い、異常があれば早期に補修することも大切です。また、耐久性の高い樹種の選択も重要な対策の一つとなります。
木の家の木材の使い方のコツ
木の家は、木の使い方・見せ方によって印象が変わります。これを踏まえ、おしゃれな木の家を作るためのポイントをご紹介していきます。
木を使う分量
木の家を建てる際には、木材を使う分量も意識しましょう。木材を多く使えば使うほど、ウッディな印象が強くなり、また、デザインに統一感を持たせることができます。反対に木材の分量を抑え、ピンポイントに用いることで木の存在感を強める、というアイデアもあります。この場合、白などのシンプルな色味と合わせれば、スッキリとしたモダンなデザインを表現することができます。
木目や色味
木目や色味の違いは、木の家の印象を大きく左右します。木目は切り出し方によって風合いが異なり、例えば、丸太の中心付近を切り出した時に現れる「柾目」は、まっすぐ平行に流れる美しい木目が特徴で、整然とした印象に。中心から少しずれた部分を切り出した時に現れる「板目」は、ランダムで表情豊かな模様を見せます。
色味に関しては、例えば、白系はナチュラルやエレガント、赤茶系はノスタルジック、あるいはアンティークな印象に。ダークブラウン系は、シックで落ち着いた大人の雰囲気を演出します。木材を着色し、好みのデザインに合わせる人も多いようです。
異素材との組み合わせ
木材と異素材を組み合わせることで木の質感を際立たせる、というアイデアもあります。金属やガラス、コンクリートといった無機素材はクールな印象を持っているため、これらと組み合わせることで、木の温かみを強調させることができます。漆喰や珪藻土といった有機素材と組み合わせれば、ナチュラルで調和のとれた雰囲気を作ることができます。
梁や柱の現し
木の家を建てるなら、「真壁工法」もおすすめ。梁や柱を大胆に見せることで、ダイナミックな印象の部屋を作ります。日本に古くから伝わる工法ですが、色味やインテリアの工夫次第でモダンなデザインにすることも可能です。真壁工法は間仕切りが少なく、天井が高いため、開放的な空間を作れる点も魅力です。
木の家の人気フローリング3種
木の家の床はフローリングが一般的ですが、その中にもさまざまな種類があります。ここでは、特に人気の高い3種類をご紹介していきます。
定尺張り
定尺張りは、同じ長さの板を一定の規則性を持って並べる張り方で、日本では最もスタンダードな方法です。端から順に同じ長さの板を並べていくため、整然とした印象を与えます。施工が比較的容易で、材料の無駄も少ないのが特徴です。シンプルで落ち着いた雰囲気を作り出すため、和モダンやミニマルなインテリアに適しています。部屋を広く見せる効果もあり、小さな空間にも適しています。
乱尺張り
乱尺張りは、長さの異なる板をランダムに配置する張り方です。一枚一枚、不揃いに並べることによって、木の表情を引き立て、自然な風合いを生み出します。また、床の継ぎ目が目立ちにくいというメリットもあります。カジュアルでリラックスした雰囲気を演出するため、ナチュラルやカントリー風の部屋におすすめです。端材を有効活用できるため、ロスが少ない点も魅力です。
ヘリンボーン張り
短冊状の板の短辺と長辺を互い違いに組み合わせる張り方で、ハの字状に連続した模様がニシン(ヘリン)の骨(ボーン)に似ていることが名前の由来になっています。古くからヨーロッパの貴族たちが好んで使ってきたデザインでもあり、クラシカルやエレガントな部屋によくマッチします。施工には高度な技術が必要で、フローリング材の使い回しもできないため、コストは高くなります。
木の家のおすすめ実例集
おしゃれで快適な木の家を建てるにはどうしたら良いか。おすすめのアイデアを実例とともに紹介していきます。
木の家に合わせて家具を造作
空間に統一感をもたせるなら、造作家具がおすすめです。例えばこちらのキッチンは、床や天井に木がふんだんに使われ、同じ素材でカウンターや収納を造作しています。壁の白色と木のバランスがちょうど良く、明るく落ち着きのあるキッチン空間を演出しています。

木の造作家具は、空間のアクセントにも使えます。こちらのホテルライクな寝室では、黒い壁面に木の造作収納棚がよく映えています。床や天井がモノトーンにまとめられ、シックな印象を与える部屋ですが、この収納棚が空間に温かみをもたらしています。木材をふんだんに使わずとも木の家らしさをアピールできる好例と言えるでしょう。
木の家を楽しむならウッドデッキ
木の家の外空間も楽しみたいという方には、ウッドデッキはいかがでしょうか。こちらの事例はウッドデッキを広く取り、板張りの屋根を設けています。水場も設置しているので、気候の良い時期にはここで食事を楽しめます。また、ウッドデッキは裸足で歩いても気持ちよく、子供たちの遊び場に最適です。

こちらの事例は、リビングからフラットに繋がるウッドデッキ。色味や質感を内装と合わせることで、空間に統一感と広がりがもたらされています。大きな掃き出し窓を開け放てば、ひと続きの大空間が生まれるため、大人数でのホームパーティーなどにも活用できるでしょう。
木の家の外観は木目で個性的に
こちらの事例は、白い外壁をベースに板張りを効果的に施した外観。漆喰の白とレッドシダーの対比が美しく目に映ります。木、漆喰に加え、ポーチの床には鉄平石を使用していて、自然素材をバランスよく組み合わせた玄関となっています。来訪客を温かく迎えるのにふさわしい場です。

こちらは、灰黒色の焼杉板が張られた外観。木を使った住宅は茶系の色をイメージしがちですが、スギを焼いて炭化させることで独特の色合いや風合いを楽しむことができ、耐候性や耐久性といった機能性も高めています。コストやメンテナンスを考慮し、道路から見えない北側と東側の外壁にはガルバリウム鋼板を採用しています。
まとめ
日本の家づくりにおいて、木は古くから重宝されてきました。時が流れ、技術が発達し、さまざまな材料を選択できるようになっても、木の重要性は今なお変わりません。
木の家を建てるなら、私たちが手がける「SE構法」にぜひお任せください。これは木造建築技術の一種で、柱と梁と耐力壁で強固な躯体を構成し、自由な空間デザインと高い耐震性を実現します。安心安全で居心地がよく、長く住み続けられる木の家を一緒に作っていきましょう。
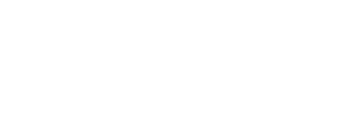
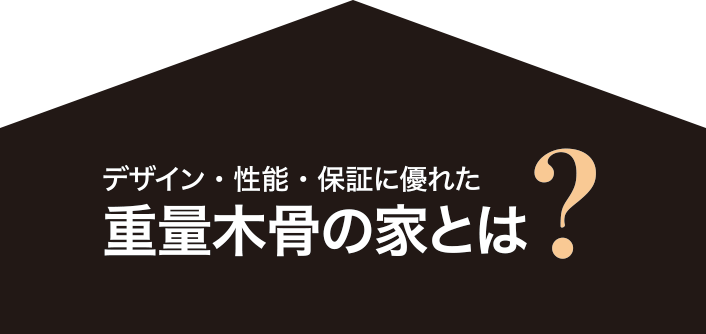























 はこちら
はこちら