完全分離型二世帯住宅で税金対策?メリットデメリットやおすすめの間取りを解説!

完全分離型二世帯住宅で税金対策?メリットデメリットやおすすめの間取りを解説!のインデックス
近年ますます人気が高まる二世帯住宅。その中でも、今回は「完全分離型二世帯住宅」についてご紹介します。親世帯と子世帯がそれぞれの生活リズムを守りながら、いざという時はお互いに協力し合える。そんな完全分離型の魅力を知って、お互いが気持ちよく暮らせる住宅づくりの参考にしてみてくださいね。
完全分離型二世帯住宅とは?

完全分離型二世帯住宅とは、親世帯と子世帯が一つの建物で暮らしていながらも、それぞれの住空間が完全に分かれている住宅タイプのことを言います。個々の居室はもちろん、キッチン、浴室、トイレ、玄関など、住宅の主要な設備の全てにおいて各世帯専用のものが設けられ、それぞれが独立して生活できる環境が整えられています。
二世帯住宅の種類

二世帯住宅のタイプは大きく分けて3種類。完全分離型のほかに「同居型」と「一部共有型」があり、それぞれの特徴を解説していきます。
同居型
同居型は、親世帯と子世帯がほぼすべての生活空間を共有するタイプ。リビングやキッチン、浴室などを共用するため、世帯間の交流が密になりやすい点がメリット。また、建築コストを抑えやすく、住宅のスペースを有効活用できます。ただし、生活リズムや価値観の違いによるストレスが生じやすく、プライバシーを確保する工夫が必要です。
一部共有型
一部共有型は、水回りなどの一部のスペースのみ共用し、他の生活空間は独立しているタイプ。同居型よりもプライバシーを確保しやすく、適度な距離感を保てるのが特徴です。共用部分を持つことで建築コストを抑えられる一方、使い方について事前にルールを決めておかないとトラブルに発展してしまう可能性があります。
完全分離型二世帯住宅のメリット
プライバシーを確保しやすい

完全分離型二世帯住宅のメリットの一つは、世帯間のプライバシーを確保しやすいこと。キッチン、浴室、トイレといった主要な設備が完全に分かれているため、自分たちの生活リズムで使用することができます。玄関も分離されているため、早朝に外出したり、夜遅くに帰宅したりする場合に物音が気になりにくいという利点もあります。
いざという時にお互いを頼れる

いざという時にお互いを頼れる点も、完全分離型二世帯住宅の魅力の一つ。物理的な距離が近いため、怪我や病気などの緊急時にすぐに駆けつけることができ、お互いに安心して暮らすことができます。また、子世帯は親世帯に育児を手伝ってもらいやすく、高齢の親世帯は子世帯からのサポートを受けやすいというメリットがあります。
光熱費の分担を明確にできる

光熱費の支払い分担を明確にしやすいというメリットもあります。同居型や一部共有型の場合、世帯ごとのエネルギー使用量が曖昧になりやすく、支払いの分担で揉めてしまうことがあります。ガス・水道・電気の設備を世帯ごとに分け、メーターも別々にしておけば、それぞれの世帯で使用した分だけ支払うことができます。
希望のデザインを反映させやすい

世帯ごとに住空間が独立しているため、希望のデザインを家づくりに反映させやすく、内装や家具はもちろん、間取りや設備に関しても自由にカスタマイズすることができます。例えば、子世帯は家事効率を重視した間取りに、親世帯はバリアフリー設計にするなど、それぞれのライフスタイルに合った空間づくりが可能です。
完全分離型二世帯住宅のデメリット
土地代や建築費用が高い
完全分離型二世帯住宅は、一般的な住宅や同居型・一部共有型の二世帯住宅に比べて、土地代や建築費用が高くなる傾向にあります。大人数が一つの建物で暮らすためには、広めの土地を用意したり階数を増やしたりする必要があり、キッチンや浴室などの設備に関しても二世帯分を用意しなくてはならないため、その分コストがかかります。
光熱費が二世帯分かかる
光熱費が二世帯分かかることも、デメリット。キッチンや浴室などの設備が世帯ごとに分かれているため支払いを分けやすい一方、トータルでは割高になってしまう点に注意が必要です。費用分担を明確にしたい場合は完全分離型、コストパフォーマンスを重視する場合は同居型や一部共有型を選ぶと良いでしょう。
コミュニケーションが減る可能性も
互いのプライバシーを尊重しやすい反面、日常的なコミュニケーションが減ってしまう可能性もあります。顔を合わせる機会が少なくなることで、関係が希薄になったり、高齢の親世帯が孤立しやすくなったりする点に注意が必要です。住宅の一部に共有スペースを設けたり、定期的に食事を共にしたりするなど、適度な交流を持ち続ける工夫が重要です。
完全分離型二世帯住宅の間取りタイプ

完全分離型二世帯住宅の間取りには、建物を上下で分ける「横割りタイプ」と、左右で分ける「縦割りタイプ」の2種類があります。
横割りタイプ
横割りタイプは、親世帯と子世帯を上下のフロアで分ける間取りタイプ。限られた敷地でも建てやすく、建築コストを抑えやすいというメリットがあり、縦割りタイプよりも多く見られます。その一方で、足音や生活音が下の階に響きやすいため、配慮が必要になります。1階に親世帯、2階以上に子世帯を配置する構造が一般的で、親世帯の上下階移動の負担を減らすことができます。
縦割りタイプ
縦割りタイプは、親世帯と子世帯を建物の左右で分ける間取りタイプ。一戸建てが横に並んでいるイメージを持つと分かりやすいでしょう。各世帯が1階から2階(あるいは3階)までの全てのフロアを使用する構造が一般的ですが、親世帯が高齢になると上階部分を使わなくなってしまうことがあります。また、広めの土地が必要であることも留意しておきましょう。
完全分離型二世帯住宅は税金がお得?

完全分離型二世帯住宅を建てる際、「構造上の独立性」(壁やドアなどで世帯が遮断されていること)と「利用上の独立性」(玄関・キッチン・トイレが世帯ごとに設けていること)という二つの条件を満たすことで、二世帯分の税金控除が適用される場合があります。ただし、自治体や年度ごとにルールが異なる場合があるため、事前の確認が必要です。
不動産取得税
不動産取得税の軽減措置を受けるためには「50㎡以上240㎡以下の床面積」が必要で、最大で1200万円の控除を受けることができます。完全分離型二世帯住宅を建てる際、それぞれの世帯の独立性が認められれば、2倍の2400万円の控除を受けられる場合があります。
固定資産税
固定資産税に関しては、1世帯あたり120㎡まで税額を半減させられる控除があります。この場合も二世帯それぞれの独立性が認められれば、2倍の240㎡までが控除に適用されます。期間は新築から3年間で、「50㎡以上280㎡以下の床面積」であることに加え、一定条件を満たす必要があります。
住宅ローン控除
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、年末のローン残高に応じた一定額が所得税や住民税から控除されます。一定の要件を満たせば、毎年控除が受けられ、最大13年間適用されることもあります。完全分離型二世帯住宅の場合、共有登記か区分登記にしておけば、それぞれの世帯が住宅ローン控除を受けられるようになります。
相続税
相続税には「小規模宅地等の特例」というものがあります。小規模宅地とは330㎡までの土地を指し、この特例によって相続税評価額を最大80%削減することができます。完全分離型二世帯住宅を相続する場合は、区分登記ではなく共有登記の場合のみ適用されます。つまり、親世帯と子世帯が同居していたとみなされる必要があり、独立性を重視する上記3つの控除(不動産取得税・固定資産税・住宅ローン)と大きく異なるポイントです。
完全分離型二世帯住宅で後悔しないためのポイント
住宅の設計
完全分離型二世帯住宅で後悔しないためには、親世帯と子世帯の両方が暮らしやすい設計で家を建てることが大切です。それぞれの要望を聞き入れながら居住スペースの割り振りを決め、部屋のレイアウトを柔軟に変更できる設計にしておくと、後々の対応が楽になります。また、世帯間の距離が近く音が響やすいため、壁や床、天井に防音対策を施し、音漏れを最小限に抑えましょう。
生活上のルール
世帯間の物理的な距離が近く、日常的な接触が避けられないため、生活ルールを決めておくことも非常に重要となります。例えば、共有スペースの使い方や、互いの家を訪問する時間帯、ゴミの処理方法などを事前に取り決めておくことで、無用な衝突やストレスを避けることができるでしょう。ルールを決めて守るだけでなく、お互いの生活スタイルを尊重し、理解し合うことも大切です。
支払いの分担
光熱費や税金、住宅の修繕費などの支払い分担についても、事前にルールを決めておきましょう。光熱費に関しては、使用した分を世帯ごとに支払うのか、どちらかの世帯がまとめて支払うのかを決めておくと良いでしょう。その他のランニングコストに関しても負担する項目や割合を事前に決めておけば、後々の支払いがスムーズになります。
完全分離型二世帯住宅のよくある質問
完全分離型がおすすめなのは、どんな人?
完全分離型二世帯住宅は、プライバシーを確保したい方におすすめの住宅です。玄関やキッチン、浴室などを別々にすることで、お互いの干渉を最小限に抑えつつ、必要な時には助け合うことができます。早朝の外出や夜遅くの帰宅が多いなど、生活時間が世帯間で大きくずれている場合も、住居を分けることで気兼ねなく暮らすことができます。世帯ごとに主要設備が完備されているため売却や賃貸の需要が高く、資産価値を重視する方にも向いています。
必要な土地の広さは?
完全分離型二世帯住宅は、一般的な住宅や同居型・一部共有型の二世帯住宅よりも広い土地が必要になります。最低でも40坪程度は確保したいところですが、家族構成や生活スタイルによっては50~60坪以上の広さが必要となる場合もあります。親世帯と子世帯を建物の左右で分ける「縦割りタイプ」は広めの土地が必要で、上下で分ける「横割りタイプ」は比較的コンパクトな土地でも対応できます。
建築費用はどれくらい?
完全分離型二世帯住宅の建築費用は高額になりやすく、2,500万円から5,000万円程度が目安とされています。土地の価格や、広さ、材料、工法など、さまざまな要因によって大きく変動し、より複雑な設計の場合はさらに費用がかかる場合があります。コストを抑えるには、間取りやデザインをシンプルにしたり、設備のグレードを抑えたりするなどの方法があります。
親が亡くなった後の使い道は?
親が亡くなった後の使い道の一つは、子世帯が住み続けるという方法。空いたスペースを趣味部屋に活用したり、広々と生活できるようにリフォームしたりするケースが多く見られます。将来的に子世帯が自分たちの子どもに譲ることも可能です。また、親世帯のスペースを切り離して売却したり、貸し出したりするという選択も見られます。こうした選択ができるのは完全分離型ならではのメリットです。キッチン、風呂、トイレなどが完備されているため資産価値が高く、ある程度の需要が見込めます。
新築と中古、どっちがいい?
親世帯と子世帯、両方の希望に沿った住宅を求めるなら、新築をおすすめします。二世帯住宅は一般的な住宅と比べて物件数が少なく、完全分離型はさらに少なくなります。設備が新しく、長く安定して暮らせる点も新築のメリットです。一方、中古で購入する場合はコストを抑えやすいため、新築では手に入りにくい好立地の物件を選べる可能性があります。また、引き渡しまでの時間がかからないため、新生活を早く始めたい方にもおすすめです。
完全分離型二世帯住宅の実例5選
玄関内部からもつながる設計

親世帯と子世帯の玄関を左右に配置した、こちらの住宅。玄関を上がってすぐの場所に互いの家に通じる引き戸を設け、特にお孫さんが自由に行き来しているとのこと。二世帯住宅ならではの距離感で、気軽な交流を生み出しています。親世帯は1階に配置し、生活しやすいコンパクトな動線がポイント。子世帯は2階を丸ごとLDKとし、3階は居室専用フロアとなっています。
土間と吹き抜けで空間を共有

二つの世帯を南北に並べた、縦割りタイプの住宅です。親世帯、子世帯ともに眺めの良い2階にLDKを配置しています。共用の土間リビングは庭に面して設けられ、集まって食事を楽しんだり、畑作業の休憩をしたり多目的に利用できます。上部は吹き抜けになっていて、抜群の開放感。この吹き抜けを通る渡り廊下から互いの家を行き来することができます。
フラットな造りは安全で快適

こちらの住宅は、コの字型に凹んだ形状の平屋造り。中庭から各部屋に光が差し込む明るい設計で、屋根勾配に沿った高めの天井が開放感をもたらしています。あらゆる住宅タイプの中でも、平屋は二世帯住宅に特におすすめ。バリアフリー設計がしやすく、年齢や体力に関係なく快適に暮らすことができます。上下階で生活音を気にする心配もありません。
共用ライブラリーで家族だんらん

本が大好きというご夫婦の要望に応え、リビングの中にライブラリースペースを設けました。一角には親世帯と子世帯を行き来できる扉が設けられ、このライブラリーが親子三代の交流の場となっています。木をふんだんに使った内装と、大開口から覗く植栽のグリーンも相まって、あたたかく穏やかな家族のだんらんを実現しています。
親子のこだわりを建て替えで実現

もともと親世帯が住んでいた家を二世帯住宅として建て替えたこちらの事例。親子のこだわりを反映させた個性的な住宅に仕上がりました。親世帯の寝室は、グリーンのファブリックと深みのある木目で落ち着いた印象に。子世帯の寝室は高級ホテルのような装いで、ウォークインクローゼットやパウダールームを設けた華やかな空間となっています。
まとめ
二世帯住宅が人気を集める背景には、社会全体の高齢化や共働き化などがあります。二世帯住宅の中でも完全分離型は、親世帯と子世帯のそれぞれのプライバシーを確保しながらお互いを頼りやすく、時代のニーズに最も適した住宅と言えるでしょう。「重量木骨の家」では完全分離型をはじめ、二世帯住宅のさまざまな実例をご紹介しています。豊富な施工アイデアをもとに、親子が快適に暮らせる家づくりを叶えてみてくださいね。
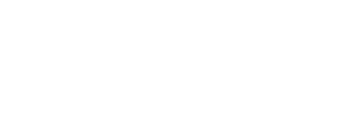
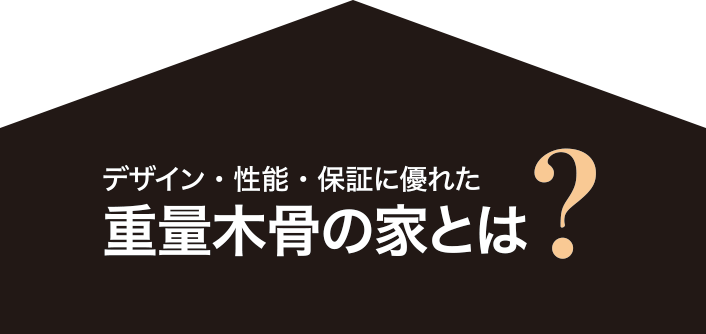









 はこちら
はこちら