【実例紹介】狭小住宅で失敗しない7つのポイントと、賢い収納で広さを活用するための間取り術

【実例紹介】狭小住宅で失敗しない7つのポイントと、賢い収納で広さを活用するための間取り術のインデックス
通勤・通学や買い物などの生活面でメリットの大きい都心部でのマイホームづくり。最大の悩みどころは確保できる土地の広さではないでしょうか。十分な広さと余裕のある家での暮らしに憧れる一方で、現実的には土地の値段が高かったり、周辺に建物が密集していたりと何かと制限が立ちはだかり、理想との折り合いをつけるのが難しいこともあるでしょう。そんな、都心部における様々な敷地条件の狭小地であっても、快適かつ理想的な住まいを実現するための工夫やポイントをご紹介します。
1.狭小住宅のメリット
最近は、都心に狭小住宅を建てたいと言う方が増えてきています。狭小住宅を選ぶことで、どのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
1-1.都心部で家が持てる
都心部の人気エリアは、一坪あたりの価格も高額のため、土地の購入だけでも多額の資金が必要です。しかし、都心部は、通勤・通学がしやすく、何かと周辺施設が充実しています。おしゃれなカフェのある繁華街や、映画・美術館などの文化施設・娯楽施設にも、気軽に行くことができるなど、簡単には諦めきれないほどの高い利便性があります。
都心部(人気のエリア)で便利な暮らしが叶うマイホームを持つことが、コンパクトな土地に建てる狭小住宅の最大の目的と言ってもいいかも知れません。
1-2.洗練されたスタイリッシュな外観
なぜ狭小住宅には、シンプルで洗練された外観が多いのでしょうか。それは、内部のデザインと関係があります。コンパクトな土地に、希望の条件の居住空間を作り出す必要がありますので、通常の家づくりとは異なるデザイン手法が求められます。結果、デザイン力の高い設計者が、設計することが多くなってきます。それにより内部空間はもちろん、外観に関しても、その高いデザイン力が発揮されるという訳ですね。
1-3.コンパクトなので掃除もラク
実際に暮らしてみた後にも、狭小住宅のメリットはあります。それは、住空間が小さくコンパクトにまとまっている分、掃除がしやすいという事です。大きな空間も憧れますが、掃除をするとなると大変です。例え掃除は週末だけと決めていても、休日の大半を掃除の時間に充てなければいけないというのは、大変なストレスになるでしょう。その点狭小住宅であれば、目についた汚れはすぐに掃除できますし、空間がコンパクトなので、毎日掃除することも可能です。
2.狭小住宅は税金も安く抑えられる
また、家を持つと発生する税金として「固定資産税」と「都市計画税」がありますが、狭小住宅であれば毎年支払わなければならない、これらの税金を安く抑えることができます。税額を決定する際、「固定資産税評価額」(単に「評価額」とも言います)に、税率をかけて算出します。この「固定資産税評価額」は土地の面積に応じて減額されるため、「小規模住宅用地」と呼ばれる200平方メートル以下の土地ならば、実はとても有利になるのです。
・固定資産税
小規模住宅用地―6分の1に減額した評価額×税率
一般住宅用地(200平米を超す部分)―3分の1に減額した評価額×税率
・都市計画税
小規模住宅用地―3分の1に減額した評価額×税率
一般住宅用地(200平米を超す部分)―3分の2に減額した評価額×税率
※東京都23区内の場合(税率は自治体によって異なります。)
また、家を建てることを法的に認めてもらう建築申請にかかる費用、土地や建物を自分名義にするための登記費用を安く抑えることができるのも狭小住宅の特徴です。家を建てるときに絶対にかかるイニシャルコストや毎年発生するランニングコストである税額を圧縮できることはとても大きなメリットです。
3.【狭小住宅で失敗しない7つのポイント】コンパクトな土地の問題点と工夫
人気の都心部にマイホームを持つことができるとはいえ、コンパクトな土地の問題点が気になる方も多いでしょう。そこで、狭小住宅の問題点をご紹介しつつ、それでも快適な住まいづくりができるように失敗しないためのポイントを解説します。
まず、狭小住宅の問題点としては、以下のものがあげられます。
・お隣の家が近い
・敷地ぎりぎりに建てて後悔することも
・縦に長くなる生活動線
・空間が単調になりやすい
・縦に長く横からの衝撃に弱くなりやすい
・建築コストが高くなることがある
・家の高さに制限があることも
このような点に対して、解決するポイントをご紹介します。
3-1.お隣の家が近い
住宅が密集しているエリアに家を建てるということは、お隣との距離も近くなるため、音や匂いが、ダイレクトに伝わらないようにする工夫は必要になってきます。防音の対策としては、防音性能の高い窓を付ける事も有効です。また、隣家と窓の位置が合わないように気を付けるだけでも、音や匂いがダイレクトに伝わるのを防ぐことも出来ます。隣家の住人と目線が合うという事も、防ぐことが出来ます。事前に、隣家の窓の位置なども調べてから、設計をスタートさせることをお勧めします。
3-2.敷地ぎりぎりに建てて後悔することも
お隣との距離が近すぎた場合、例えばエアコンの室外機などの設置に困ることになるでしょう。そんな時には、部屋のプランニング上、人が出入りできるバルコニーが設置出来れば理想です。もしそれも厳しい場合は、室外機が置ける小さめのバルコニーを設置できるように、計画しましょう。
また、将来的に外壁の塗装などのメンテナンスが必要となった際は、狭小地用の奥行きが浅い足場板などもあります。法律上の隣地からの空き寸法を守っていれば、メンテナンスにも対応できるでしょう。
3-3.縦に長くなる生活動線
狭小住宅は、2階建て・3階建てにすることが多くなります。そのため、どうしても上下の動きが多くなるという事で、「生活動線」や「間取り」には工夫が必要です。毎日の手間で考えるなら、まずは家事動線をいかに短くするかという事をポイントに考えるといいですね。例えば、キッチンやバスルームといった水周りを、極力近くに配置するのはもちろん、洗面と洗濯、物干し、収納などの用途を一箇所にまとめると、日常の家事をワンフロアで済ますことが出来ます。
3-4.空間が単調になりやすい
床面積がコンパクトなので、部屋を壁で仕切ってしまうと、どうしても閉塞感のある空間になってしまうということも。そこで、工夫された手法として「スキップフロア」があります。用途ごとに床の高さを少しずつ変えることで、間仕切り壁を作らずに領域の違いを演出できるところが魅力です。壁がないぶん、目線は遠くまで届くことで、同じ空間であっても開放感を感じられます。
また、開口部を各部屋に作りにくい時にも、日当たりのいい手前の部屋から、奥の部屋まで光が届くというメリットもあります。他にも、吹抜けやストリップ階段などを使って、明るく自由な空間を作ってみましょう。
3-5.縦に長く横からの衝撃に弱くなりやすい
狭小住宅は、2階建て・3階建てと縦方向に空間をとっていくので、地面に接している面積よりも、縦の面積(高さ)の方が大きくなります。そこで重要になってくるのは、きっちりと構造計算された建物であるかどうかという事になります。例え木造であっても、狭小住宅を建てる場合には、構造計算された建物であると安心できます。
3-6.建築コストが高くなることがある
狭小住宅は縦方向に長く、3階建てや地下にも居住空間を作る場合があります。そうすると建築費は上がります。コストを抑える方法のひとつには、内装をシンプルにすることがあげられます。
また、スキップフロアなどで、壁が少なくなるというのも、プラン上のメリットにもなりますね。また、狭小住宅の施工事例が多い建築会社は、経験も豊富でコスト管理にたけていますので、そういった建築会社に頼むというのも大事なポイントです。
3-7.家の高さに制限があることも
建物を建築する際には、当然建築基準法や、その他関係法令を守って建てなければなりません。その一つには、高さの制限があります。地域ごとに、どの程度の高さまで建てられるかが、法律で決まっているので注意しましょう。ただ、狭小住宅が建つような都心部では、だいたい3階建て以上は建てられることが多いので、そこまで心配する必要はないでしょう。
その他にも、隣地や前面道路などに。日陰を多く作ってしまう事を避けるために、建物の一部を削る必要がある場合もあります。そのようなきには、部屋内部の天井が一部低くなることもありますので、最初の段階から天井が低い部分が、デッドスペースにならないように工夫が必要ですね。
4.狭小住宅でも後悔しない!有効な間取りとは?
これまでもご紹介してきたように、狭小住宅は生活できる面積が狭くなるため、通常以上に間取りの工夫が肝要です。せっかく便利なエリアに建てたマイホームで後悔しないためにできる工夫を見ていきましょう。
4-1.空間を完全に区切らない

寝室など、よっぽどプライバシーが求められる居室以外は、できるだけ壁で区切らないことで開放感を演出することができます。
特に人気があるのが、上記でも触れた「スキップフロア」。1.5階または2.5階をつくれば、緩やかにつながりつつも段差そのものが「区切り」としての機能を担ってくれるため、視界を遮ることなく空間を分けることができるようになります。段差も人の身長ほど大きくすれば、壁がなくとも1.5階ないしは2.5階はほぼ視界に入れないようにすることもできます。
また、「スキップフロア」のもう1つの利点は移動が階段だけで完結すること。階段と各層の一部を通過することで移動ができますので、廊下が不要となりその分を各層の居住スペースに当てて広くすることができるのです。一般的に廊下の幅は80センチとされていますので、この分を居室スペースに回すことができるのは、狭小住宅には大きなメリットだと思いませんか?
4-2.地下室を設ける
スキップフロアとあわせて、「地下室」「半地下室」を設けるのも一案です。地下室をつくると建築コストが少し高くなってしまいますが、長く住むことを考えて多少コストをかけても良いという考えであれば、必要な居住面積を「地下室」ないしは「半地下室」に担ってもらい、さらに空間を増やすことができます。
映画鑑賞や楽器演奏のための趣味の部屋にすることもできますし、湿気や雨に対応できる設備を設けて静かな寝室としても良いでしょう。
また、一定の基準下で設計された地下室は容積率に算入しなくてもよいとされているため、スペースの確保法としては充分検討する価値があります。
4-3.ロフトや中庭をつくる
狭小住宅だと、どうしても家そのものも小さく狭く感じてしまいがちになります。それを縦に伸ばす方法のひとつとして、ロフトを設けるという方法があります。ご存知の通り、ロフトとは居室の一部を高くして、2層にした部分のことを指します。
ロフトを設けるには天井までの高さが1.4メートル以下であることや、はしごを固定しないなどいくつかの条件がありますが、秘密基地のような寝室や収納、趣味のスペースを増やすことができるため、狭小住宅の工夫としては有効な手段です。
さらに、小さくとも中庭をつくることも選択肢の1つです。入り口が狭く奥行きが長い、いわゆる「うなぎの寝床」と呼ばれるような細長い土地である場合、明るさや風通しを良くする方法として中庭が活躍します。見た目に広さを感じさせてくれるだけでなく、小さいながらも家庭菜園を楽しむなど日常的に自然を感じることもできるようになりますよ。
5.狭小住宅での収納スペース創出法
狭小住宅では、収納スペースをどのように確保するかも悩みどころです。効率よく収納スペースを確保するにはどのような工夫ができるでしょうか。
5-1.暮らしに必要な「モノ」の見直し
スペースを確保するよりも先にしておくべきことは、自分たちが生活するうえで必要なモノがどれだけあるのかを把握し整理することです。極力少ないモノで生活ができるよう「断捨離」すると、持ち物だけでなく心も整理できるのではないでしょうか。「ミニマリスト」としてすっきりとしたシンプルな生活も素敵です。
5-2.「デッドスペース」の有効活用
意識しないと見過ごされがちなデッドスペースが意外とあることにお気づきでしょうか。例えば、階段の下部。なんと、ここにキッチン収納や書斎、トイレを設置するのはスペースの有効活用に適しています。もしもニオイや音が気になるという理由でキッチン収納や書斎、トイレにはしたくないのであれば、収納スペースとして利用するのも良いでしょう。
クローゼットのように閉じるタイプにすることはもちろん、見える収納として本や小物をオープンに収納するスペースにするのも素敵ではありませんか。階段の1段ごとに引き出しを設けるというアイディアもあります。日本古来の「階段箪笥」のように仕立てるのもこなれた和モダンを演出できますね。
また、収納スペースを確保しようとして、一部屋全面に大きなクローゼットを設けても結局手の届かない部分ができてしまうもの。それを逆手にとってクローゼットの一部を低めに設定してそこにベッドマットを納め、寝室にしてしまうという意外な方法もあります。

さらに、スキップフロアを採用するのであれば、その下部にも見逃したらもったいないデッドスペースが生じます。特に1階部分は、通常、人の出入りができる高さにはしませんので、こここそ上手に活用したい場所となります。
5-3.「見せる」収納法で生活用品もインテリアに
モノを目につかない場所に隠してすっきりさせるのももちろん素敵ですが、あえて見えるように収納するのも個性を発揮できる収納方法として素敵です。特にキッチン周りはうまくいけばおしゃれな雰囲気を醸しつつ、出し入れする手間を省くことができるため便利でもあります。
例えば、コンロ周りにフライパンやフライ返し(ターナー)などのキッチンツールを釣り下げてみるのはいかがでしょう。この時のポイントは色や素材を極力統一することです。
こうすれば、必要なモノにすぐ手が届くし、洗ったらすぐに掛けておけるうえ、キッチンツールのためだけの収納スペースをつくる必要がなくなります。
5-4.狭小住宅こそ選択すべきは「造り付け家具(造作)」
スペースがどうしても制限される狭小住宅を充実させるためには、造り付け家具(造作)がおすすめです。
上記のとおり、最低限必要なモノの量と、それをどこに収納すれば生活動線として効率が良いかの判断できれば、家を建てる段階で、棚やクローゼット、テレビ台、キッチン収納、とテーブルや収納つきベンチまで、ご家庭にマッチしたこだわりの家具を作ってもらえます。
もちろんそのための費用は別途で発生しますが、狭小住宅に合う家具がなかなか見つからない・家具が搬入しづらいといった問題を回避でき、ぴったりサイズの家具に揃えることで空間をよりよく活用することができ、居心地の良い部屋をつくることができるでしょう。
設計段階で建築士の目でデッドスペースを洗い出してもらえるだけでなく、内装全体のイメージを壊さないように考えてもらうことができるので、無理にDIYする必要もなく、入居と同時に必要な家具が揃った状態で生活をスタートすることができます。
6.【実例紹介】狭小住宅が魅力的である理由
様々な工夫を凝らした狭小住宅の事例をご紹介いたします。狭小住宅を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
6-1.狭小住宅とは思えない開放感を実現
各部屋の壁や天井高の調整でどうしても窮屈な印象になりやすい狭小住宅でも、大きな吹き抜けを設けて、遮る壁を廃した大空間を作り出しています。開放感あふれるマイホームの夢が叶った事例ですね。
6-2.設計の段階から計画的にスペースを確保
ロフトというと狭くて光の当たりづらい場所をイメージされるかもしれませんが、こちらの実例をご覧いただければイメージが一転するはず。広いだけでなく明るさも十分にあり収納スペースにしてしまうにはもったいないほど。居室としても趣味を楽しむプライベートな空間としても色々な楽しみ方ができる空間になっています。
6-3.土地条件を生かした地下ガレージ
通常、地下室などを設けるには、一般の木造住宅の建築では使用しないような重機が必要となるとご紹介しましたが、もともの敷地条件を上手く活用すれば賢く駐車スペースを確保することもできますよ。
6-4.高天井と連続窓で広々としたLDK
敷地面積、約20坪という土地に建つ狭小住宅。その中に家族の為のスペースと、ご主人専用の趣味部屋、そして奥様専用のドレッサールームを入れるというリクエストに応えた、盛りだくさんの狭小住宅です。写真のLDKは、天井を出来るだけ高く作り、腰窓を連続窓とすることで、光あふれる広々とした空間になっています。内装材も、無垢材の優しい色味を使用する事で、明るさを演出しています。
6-5.狭小地の光を取り込んだL字型2階リビング
こちらは、郊外型の狭小住宅になります。住宅地という事もあり、狭小住宅としてはめずらしく2階建てです。1階にプライベートスペース、2階にパブリックスペースである、LDKを配置しています。LDKに接して広いバルコニーを設置したことで、狭小住宅とは思えない広々とした空間になっています。バルコニーは、プライバシーの確保の為に壁を高くしているので、リビングやダインニングで過ごす時にも、周囲からの視線は気にならないのがいいですね。
6-6.間口5mの南向きの吹き抜けとルーバーのある狭小住宅
こちらも、間口5mという敷地に建つ狭小住宅です。北側道路面が正面で、周辺環境の影響で、建物全体は外に対して閉じたデザインになっています。現在は南側には建物は建っていませんが、将来的に家が建った際にも、家の中に光を取り込める構造が特徴です。2階リビング上に吹抜けを作り、2層分の大きな開口を設けています。また、夏には窓からの日射熱を遮るために、可動式のルーバーも設置されています。ルーバーが、パッシブデザインと建物のデザインの、両方の役目を担っています。
6-7.プライバシーに配慮したおしゃれな外観の狭小住宅
間口の大きさが約3間の、うなぎの寝床状の敷地に建つ狭小住宅。正面から見ると、まるで平屋のようなデザインで、落ち着きを醸し出しています。中に入ってみると、1階には玄関と、奥様が使用するサロン。2つの空間ともコンパクトなサイズですが、間仕切りがガラスの引違戸になっているので、思った以上に広さを感じます。
このサロンは、家の正面の前庭の緑も楽しめる、第2のリビングとしても使用できます。そして2階へ上がると、LDKが表れます。夫婦2人の家らしい、落ち着いた雰囲気ながらも、勾配天井で開放感たっぷりに仕上がっています。
まとめ

敷地面積に限りがあり、建築費用もかさみやすい狭小住宅。住むエリアの魅力や利便性、税金を安く抑えられるなどのメリットは、長く住むからこそとても大きいものでしょう。もしくは、生まれ育った土地で家を新たにするという安心感もあるかもしれませんね。そうであれば、注文住宅でとことん「理想の暮らし」を突き詰めてみてはいかがでしょう。
その土地の持つ性格や条件にそって、最大限のメリットを生み出すこと―。これが注文住宅の最も得意とする分野です。ここまでにご説明したことで、「狭小住宅はとても難しい」「思ったとおりの家は建たない」とお思いではありませんか。いいえ、決してそのようなことはありません。狭小な土地であっても、工夫次第でオシャレで快適な、あなただけの理想を凝縮した空間にすることができます。
狭小地であるからこそ家づくりが楽しい、と思わせてくれる光景をどうぞご覧になってください。「注文住宅の楽しさ」にきっと驚かれることでしょう。
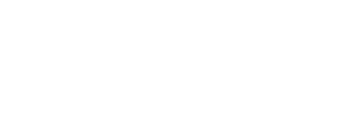
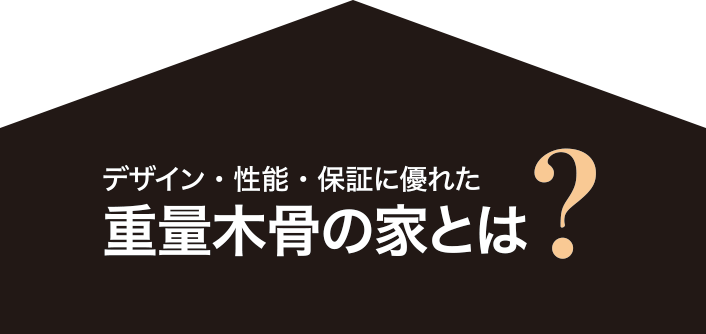






























 はこちら
はこちら